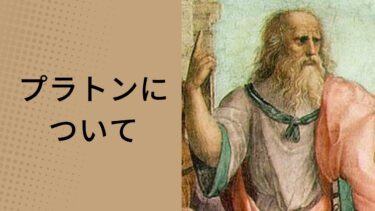哲学をするとは、難しい専門的なことを考えることではなく、日常に起こる身近な出来事について立ち止まって考えることだ。
日常には様々な疑問や悩みが付き物である。それらは、些細なものから、自分の人生に関わるようなものまであるだろう。
たとえば、ダイエット中にお菓子を食べることは悪いことなのかとか、他人との付き合いにおいて、自分はどの程度まで他者に踏み込むべきなのかとか、大小様々な疑問や悩みがある。この疑問や悩みにどのように向き合い、対処していくべきなのかという方法の一つとして哲学がある。
哲学と科学の方法の違い
たとえば、他者との関係について考えるとき、その考え方は大きく分けると二つあるだろう。
一つ目は、科学的な方法である。科学的な方法は、対象を客観的なものとして扱う。客観的であるとは、誰にとっても同じということである。つまり、私と対象との個別の関係や、対象の固有性・個別性を排除し、すでにある他のものとの共通点で括り、一般化するということである。他者との関係でいえば、私の具体的で個別の悩みに対して、「それは、〇〇代の〇〇の傾向にある人によく見られるもので、〇〇という名前で呼ばれますね」というような答えを返す。時には、解決策を提示するかもしれない。
こういった方法は、物理的なものを説明する場合には有効であるが、人の感じ方や関係、人生といった主観的なものを説明する場合には、不十分である。なぜなら、人は物理的な対象とは異なり、自分自身の主観的な世界をもっているからである。人には、自らが感じ、考え、悩み、生きるという自らの中の世界がある。この世界は自分の主観的な世界であり、人はこの主観的な世界を生きている以上、それを排除し、一般的なことを言われたところで、それに意味を見出せない。極端なことを言えば、「あなたの人生は、〇〇の人生と同じです」と言われたらどう思うだろうか。たとえ客観的な共通点がいくつかあったところで、私にとっては私の人生でしかないと思うだろう。となると、自分であること、主観的であることが重要な問題に関しては、その主観を維持したまま考える方法が必要である。
その方法として、哲学がある。哲学は、自分にとっての世界、主観的な世界から出発する。そして、その主観的であること、自分が自分の人生を生きているという固有性を維持したまま、その主観的な世界に生じる疑問や悩みを取り出し、それについて考えることができる。つまり、自分が実際に感じ、考え、悩んでいるということ、その現場からそのまま哲学が始まるのである。たとえば、よく生きるとはどういうことか、正しいとはどういうことか、何かが美しいとは一体どういうことか、といった問いである。これらは、真善美と呼ばれる哲学の中心的な問いだが、これも元々は、「良く・正しく・美しくありたい」という個人の思いから始まった問いである。
そもそも、人が何かに悩み、考えるのは、自分自身や、自分の人生についてであろう。それゆえ、哲学の歴史が、西洋も東洋も紀元前から続いているのだろう。
主観的なものに論理を与える意味
私が生きているというこの主観的な事実から問いを始め、考えていくのが哲学であると述べた。とすると、私さえ納得できればいいとか、他人の意見は関係ないとかいった考えになるかもしれない。しかし、哲学は単に主観の世界に閉じこもっていることを推奨するのではない。自分が感じる疑問や悩みを問いの形にして、それに対して答えを与えようとする。それが、哲学をする上で欠かせないプロセスだ。
では、なぜ問いの形にすることが大事なのか。それは、問いを立てることが、主観的な疑問や悩みに、言葉という形を与え、自分から独立した存在にすることができるからである。つまり、言葉を与えることで、主観的な問題を、客観的な形式に変えることができるのである。先ほどの科学的な方法は、この問いを立てる前の段階から、客観的な世界を前提とし、主観性を排除していたのに対し、哲学的な方法は、主観的な世界から出発しつつも、自分だけの世界にとどまらずに、それを言葉として表し、そこに論理を与えていくことを通して、その疑問や悩みに答えていこうとする。
こうした言語化や理論化といったプロセスを経ない方法もある。それは、文学や芸術といった分野である。たとえば、相田みつをの「人間だもの」という言葉がある。この言葉は、確かに言葉という形は与えら得ているが、その意味についての論理的な説明はない。つまり、読み手は、その言わんとしていることを想像し、自分なりに理解するという必要がある。この明確な意味の不在に想像力が働く余地があり、それを楽しむのがこうした芸術だが、想像力や解釈の余地があるがゆえに、曖昧さを残すことになる。
このような曖昧さは、人によって受け取る意味が変えるし、自分自身に対してもその時によって意味を変えてしまうかもしれない。つまり、曖昧な言葉は、解釈を変動させ、その言葉が言い表そうとしていることを覆い隠してしまうことにもつながる。文学や芸術はその解釈の多様性を楽しむものだが、哲学はあたう限りその輪郭を明瞭にするために、正確な言葉遣いをする。それは、客観的な言葉遣いによって、問題を自分から切り離し、対象化することで、自分から独立して存在させるためである。これは、解釈によるその都度の恣意的な意味変更を防ぐことでもあるし、それはすなわち、問題それ自体の存在を成立させることである。
こうして、哲学的方法によって、日々の疑問や悩みという主観的な世界から生じた曖昧で形のないものは、問いという言葉を与えられて、その問いを精査していく過程で論理性を獲得することができる。そうなって初めて、その問いに答えていくことが可能になるのである。そもそも何に困っているのかわかっていない悩みに解決することはできないように、問いの立てられていないことに答えをだすことはできないだろう。
悩みや問題が解決できない大きな理由は、その悩み、問題が何なのかが分かっていないことにあるという。人は課題が与えられれば、それに向けて行動できる。しかし、何をすれば良いのかわからない時に途方に暮れる。哲学の出発点はそもそも主観的であるため、それ自体は私と区別できない。私は、それがもたらす苦悩から分離されない。私は取り外し可能なものとして悩みを持っているのではなく、私は悩んでいる私としてあるのだ。だが、その悩みを客観的な形にしてみたら、言葉を当てはめてみたら、その悩みは自分と区別された対象としても存在することになる。
長々と書いてはきたが、要するに、哲学とは、日常を生きる上で、なにか疑問に思うことや、悩んでしまうことに対して、正面から向き合い、じっくりと考えながらなんとか論理的に言葉にしていこうという営みであるといえるだろう。そして、考えるときに、論理的な言葉を使うことは、自分にとってその疑問や悩みをはっきりさせることにつながるし、誰か他の人に伝わるようにもなる。そのような思考の歴史が、哲学の歴史といっていいだろう。したがって、哲学の難しさとは、日常の様々な疑問に向き合い、それを問いの形に仕上げていくことであり、それはつまりは、日々の生活をなんとなく生きるのではなく、正面から向き合うことの難しさといえるかも知れない。