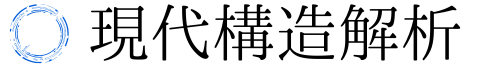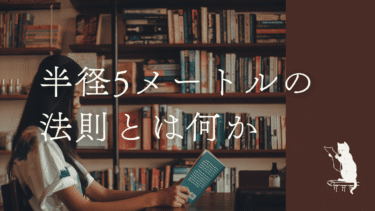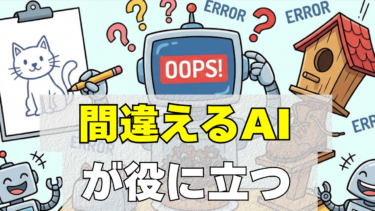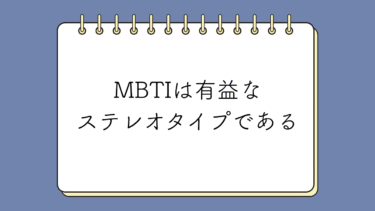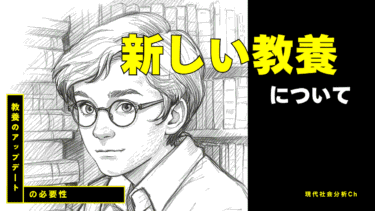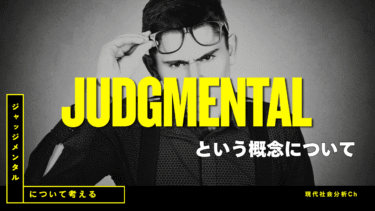フィルムカメラ、レコード、古着、喫茶店……。
いわゆる昭和レトロ的なものが流行った背景には、そのレトロさを画像として切り取って、SNSに上げるという極めて現代的な行為が原因としてあった。それに伴って、「エモい」という言葉も広まっていったように思える。
こうしたレトロさをSNSというデジタル空間内に転送することは、デジタル世界とアナログ世界を行き来する行為だといえるだろう。
ここには、昭和の時代にスマホを持ち込んで探索するような、いわば、タイムスリップ的な感覚があった。
この奇妙な時代錯誤感を楽しむという行為には、しかし、人々に蓄積していたデジタル世界への「嫌気」や「疲労」がその根底にあり、それが無意識のうちに人々をデジタル以前の世界、すなわちアナログの世界へと誘ったようにも思える。
つまり、「デジタル疲れ」が、デジタルのない世界、デジタル以前の世界へと、人々を導いたと考えられるのである。
デジタル疲れ
デジタルに疲れるのはなぜか。
デジタル化によって得られる核心的なものは、便利さである。つまり、おそらく、デジタルの便利さに疲れるのである。
しかし、便利さに疲れるとは何なのか。
デジタルは速く、手間がなく、無限である。
音楽を聴くにしても、本を読むにしても、ダウンロードすればすぐに楽しめる。わざわざ、店に買いに行く必要はない。手間要らずである。そして、配信サイトを見れば、無数のコンテンツが並んでいる。
これは、便利である。効率的である。ゆえに、良いものであるようにみえる。
だが、同時に疲れる。
なぜなら、それが選択肢を広げ、そしてその選択を修正可能にしたからである。
何でも手に入れられるが、時間は有限である。映画を見るにも時間はかかるし、労力もかかる。であれば、無限にある選択肢のなかから、良いものを選ばないといけない。仮につまらないコンテンツを選んでしまったなら、そのコンテンツの再生をやめ、また別のものを選ばなくてはいけない。
せっかく、良いコンテンツがたくさんあるのに、つまらないコンテンツに割いている時間はない。
こうして、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスという言葉が生まれた。これらの言葉は、無限に比較可能なコンテンツがあるから生まれたのだろう。
このように、多すぎる選択肢とその選択の修正可能性は、ストレスになるのである。
アナログ・物理的なものへ
アナログなものは不便である。
ものを買ってこないといけないし、その一つ一つに金もかかる。家に置いておける量にも限界がある。ゆえに、選択肢も有限にならざるを得ない。
しかし、だからこそ、限られた選択肢のなかから、じっくりと選べる。
そして、有限なもののなかから手に入れたものは、場所をとって、そこにあり続ける。処分するにも、時間がかかる。手間もかかる。
しかし、だからこそ、一度手に入れたものを、じっくり時間をかけて消費体験をすることになる。
また、物理的なものは、一つの物体としてあり、他のものからは独立している。デジタルなもののように、配信画面に他のものと並んで表示されることはない。
つまり、物理的なものは、それを手に取る人間と、一対一の関係を結ぶのである。ゆえに、それに没頭できる。
このように、アナログで物理的なものは、人に「今ここ」の時間と場所を与えるのである。
まとめ
アナログ・物理的なものは、選択肢を排除する。
何かを選ぶ際にはその選択肢を狭め、選んだ後にはありえたかもしれない選択を排除し、取り返しのつかない選択にする。
しかし、その選択肢の排除という不自由が、今目の前にあるものと、一対一で、集中して向き合えることにつながることになる。
そこにアナログで物理的なものの魅力がある。
ある意味で、アナログなものは、現代の「自由という刑」からの解放なのかもしれない。