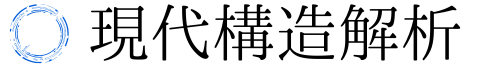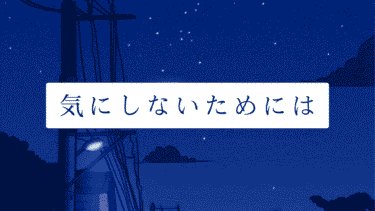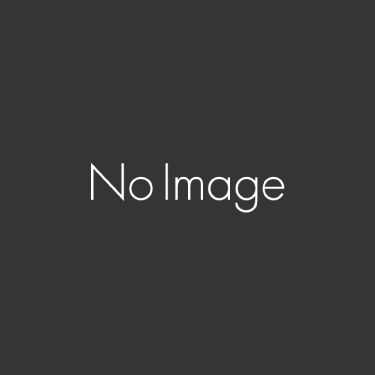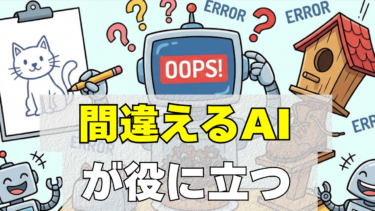おそらくここ数年、飲食店やホテルなどのサービス業の接客の距離が近くなっている。あるいは、接客態度が緩くなっていると思われる。
この記事では、接客が緩くなり、距離が近くなっている具体的な例を挙げ、そして、その原因や背景について分析していく。
接客が緩くなっている例
言葉遣い
まず、言葉遣いが緩くなっている。
これは昔から指摘されていたことではあるが、かつては、言葉遣いの誤りはあっても、客に対して、接客用に丁寧な言葉を使おうという意識はあった。
だが最近は、接客において、まるで友達に対するかのような言葉遣いをするスタッフが増えているように思われる。
「いらっしゃいませ」や「ご注文はいかがしますか」といったマニュアルに則った定型的なやりとり以外の少しイレギュラーな対応になった場合に、いわゆるビジネスマナー的な言葉遣いをせずに、日常会話的な言葉遣いをする人が多いように思える。
たとえば、「〇〇ってもらえる?」と客が聞いたときに、「もらえます」と客の使った言葉で返答するといったように、接客において、尊敬語などの丁寧な言葉を使おうとすることが減り、よりくだけた言葉が使われている。
その他の接客態度
言葉遣い以外の接客態度においても、くだけた態度が多くなったように思える。
客が店員の手伝いになるようなことをしようとしたときに、それを遠慮するのではなく、「じゃあお願いします」といったような態度の店員も多い。
また、店内に客がいて、客が店員に何かを頼もうとしているのに、店員同士が喋っていることもよくあることだろう。
接客が緩くなっている原因
このように、サービス業における接客が徐々に緩くなり、距離が近くなっていっていると思われるのだが、ここでは、その善悪を問うというよりも、その原因や背景を分析していきたい。
厳しさの消滅
まず、世の中全体に、かつてのような厳しさがなくなった。
これは、何かを指導する場所で顕著である。表面上の原因は、ハラスメントという概念の登場だろうが、根本的な原因は、人手不足によって教わる側の立場が強くなったことにあるだろう。
これは、接客業において、特に顕著である。
「許される」基準の低下
そうなると、指導する側は、以前はサービスにおいて、許されなかったことを許すほかなくなる。つまり、サービスの基準を下げざるをえなくなる。
そうして、接客の基準が緩くなる。
「当然の基準」の変化
結果、客はその基準に徐々に慣れていく。そして、社会全体において、接客において想定される「当然の基準」が変わっていくことになる。
つまり、以前の接客の基準を皆が忘れ、今の基準に適応していくのである。
緩い社会への変化
このような原因によって、接客は緩く、距離が近くなっており、今後もそれが加速するものと思われる。
そして、サービス業における接客は、人が日常的に接する最も身近な他人であり社会であるため、その変化が、社会全体に影響を与えやすいと思われる。
ゆえに、緩い接客への変化は、緩い社会への変化につながるかもしれない。それは、良くも悪くも、公に対する考え方が変わり、より公私の区別が曖昧になっていくことだ。
そして、それは、アメリカ的なフレンドリーだが、ルーズな社会に近いが、今後、日本がその面でもアメリカ化するかどうかは、まだ定かではない。