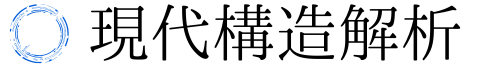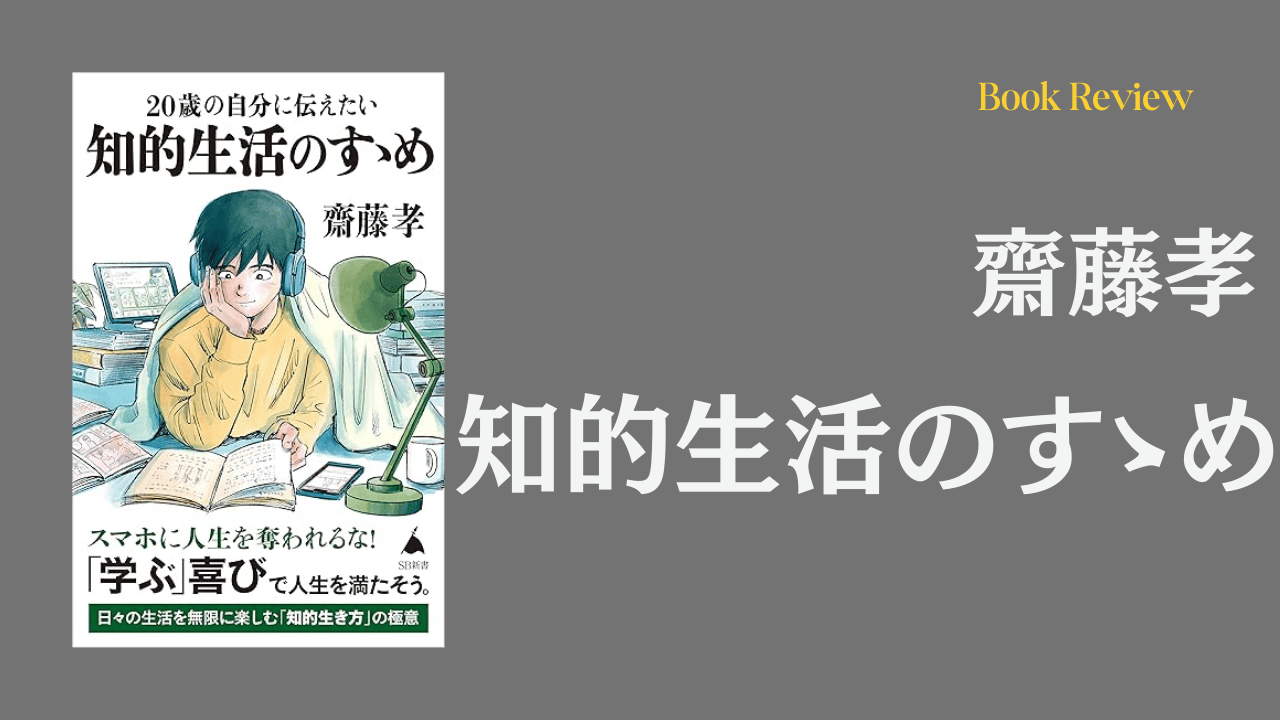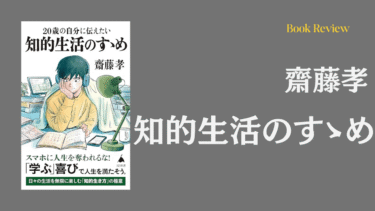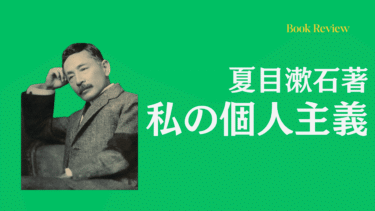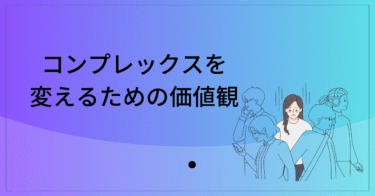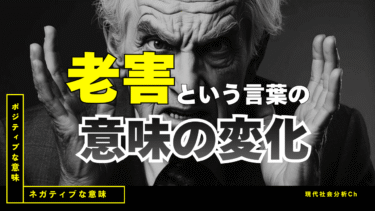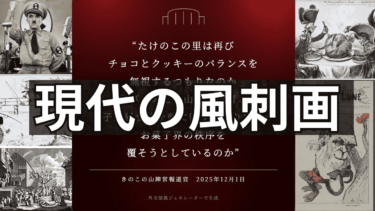齋藤孝著『20歳の自分に伝えたい 知的生活のすゝめ』は、知性や教養が軽視されがちな現代において、いわゆるインテリ層に限らず、幅広い人々に、知性的に生きること、教養をもつことをすすめている。
この記事では、本書について、以下のような観点から内容をまとめ、批評を行う。
・知的な生活とは何か?
・知的な生活の何がいいのか?
・なぜ反知性的な考えが良くないのか?
・そもそも知的になれるのか?
*本記事では、Kindle版のページ番号を使用しています。
KindleUnlimited読み放題対象

知的生活とは何か?
そもそも、本書がすすめる「知的生活」とは何なのか。これに対して、著者は、「知性を重視する生き方」だと言う。では、知性とは何か?著者はこう述べる。
(中略)知性とは、単に知識がたくさんあること、博識であることを意味しません。知識と知性は大いに関係のあるものではありますが、必ずしもイコールの関係ではないのです。 私が「知的生活」を誰にでもおすすめするのも、知性が「よく生きる」ための能力そのものだからです。(p. 4)
つまり、
・知性=知識ではないが、大きく関係する
・知性は「よく生きる」ための能力
となる。
知性と知識との違いとは何か?
知性と知識は違う、と著者は言う。それは、著者の体験に基づいている。
著者が学生時代、大学には知識が豊富な人が多くいた。だが、彼らのなかには、「淀んだ雰囲気」や「表情が暗」い人がいた。つまり、彼らは知識が豊富にもかかわらず、陰鬱としていて、楽しそうではないということだ。
これに対して、著者の考える知性は、以下のようなものである。
私が思う「知的生活」とは、もっと活き活きとした、本を読めば読むほどに活力を得られるような生活です。(p.4)
自分にとって新しい刺激になりそうなものを、なんでも貪欲に取り入れてみようとする能動的な生のあり方こそが、本当の意味で知的な生活だと思うのです。(p.4)
知性とは、それを備えることで、よりクリエイティブになり、上機嫌な精神をもたらしてくれるもの──そういう確信が昔から私にはあります。(p. 5)
知的生活=知性を重視する生き方である以上、知的=知性的と考えて良いだろう。
ということは、知性とは、
・人を活き活きとさせ、上機嫌にさせる
・人に能動的な好奇心を与えるもの
であるといえる。
つまり、著者にとっての知性とは、人間の内面的なエネルギーのようなものであるといえる。このエネルギーが人を活き活きとさせ、好奇心をもたせるのである。そして、そのエネルギーが「狩猟」の「獲物」のように向かう先が、知識なのである。
まとめると、知性と知識の違いは、知性が人間のもつエネルギーで、知識がエネルギーの向かう先といえる。
こういった知性を重視し、活き活きと、上機嫌に、知識を求めて活発に生きることが、知的生活であるといえる。
アウトプットをする
もう一つ、知的生活に必要不可欠な要素として、著者は、アウトプットを挙げる。好奇心に従って知識を追い求め、自分のなかだけで満足していては、真に知的な生活であるとはいえない、という。
その理由は、第一に、好奇心のままに知識を追い求めていく知性があれば、自然とそれを表現せずにはいられないというものだ。特に現代においては、表現方法が多様かつ手軽になっているため、なおさらである。
第二に、コンテンツが氾濫する現代において、単にコンテンツを受容し続けるだけでは「意識の拡散」(p.133)が生じてしまう。これは、コンテンツの体験が浅くなるということだ。アウトプットを前提としてインプットすることで、インプットの質が大きく向上する。そのため、アウトプットは知性にとって不可欠なのである。
知的生活の良さは何か?
知的生活の内容について理解した上で、その生活を営むことの良い点は何なのか。特に、知性が「よく生きる」ための能力であると述べられていたが、知性があるとなぜ「よく生きる」ことができるのか。
喜びを得られる
①でもあった通り、著者は、知性の「活き活き」や「上機嫌」といった感情的な面を重視している。そして、「よく生きる」についてもその延長線上で考えている。
既知の知識が未知の知識とつながった瞬間、自分の好奇心が満たされることで、他の何物にも代えがたい幸福感に浸ることができます。(p. 16)
『カラマーゾフの兄弟』のような名作を読むことでできる文豪との精神的対話は、人が人生において経験できる喜びの中でも最上級のものです。(p.83)
このように、著者は、知的生活を送ることで、好奇心が満たすことができたり、過去の偉大な人物と対話したりすることができ、結果、最上級の喜びを得られる、と考えている。
性格が明るくなる
芸術作品や文学作品を鑑賞するとき、知識があるとより深く理解できる。それは、お笑いなどのエンタメも同様である。知識は、さまざまな作品・コンテンツ体験を豊かにする。
ゆえに、知性は明るい性格を作るし、笑いをもたらすことができる。著者は以下のように述べる。
知性を磨いた結果として暗かった性格が明るくなっていき、前は笑うこともなかった人が哄笑、爆笑できるようになったというほうが、学問をする人の姿として自然に思えるのです。(p.25)
身体的所作が洗練される
一般的に知性というと、頭の良さや知識量といった頭脳的なことを想像するだろうが、知性は頭脳だけでなく、身体にも宿るものである。これを著者は、「身体の知性」とし、言語化しにくい「暗黙知」であると述べる。(p.29)
この身体的な知は、伝統的な「型」に典型的に見られる。代表的なのは、相撲や武道などの運動における型と、書道や茶道などの芸事における型だ。こういった型は、言語化しにくい身体的な知を「冷凍保存」(p.30)したようなもので、これを反復することで、伝統的に受け継がれてきた身体動作における知を習得できるのである。
こうした身体知は、振る舞い、佇まいなどに表れ、その人全体の人格や品性を表しうるものである。
反知性主義の何が良くないのか?
ます。私には「知性軽視」の風潮が、どんどん強まっている印象があります。(p. 36)
著者はこのように述べ、反知性的な風潮が若者に与える悪影響を論じる。
薄っぺらくなる
著者は、現代の若者の上品さや「整いぶり」を称えた上で、同時に、「打たれ弱く」(p.37)なり、「勇気が足りない」(p.38)ようになり、そして、「人格の厚み」(p.39)がなくなり、「薄っぺらく」(p.40)なったと述べる。
このときに著者が比較しているのは、明治、大正、昭和初期に生まれた人々である。その世代の俳優は皆、存在感があった。また俳優に限らず、一般人でもそうであった、という。
こうした存在感が生まれる原因を、著者は、歴史的に積み重ねられてきた「身体文化」や「精神文化」にあると論じ、現代人はこれが失われ、「個人が個人の資質だけで勝負しなければいけなく」(p.41)なってしまったからだ、とする。
(中略)現代人の内面世界が、その人自身の「気質」だけで構成されていて、その気質を下支えする土台や、柱・梁にあたるものがない(略)(p. 40)
このように、著者は、人の精神が、個人の資質と、それを支える文化的な資質の両方から成り立っていると考えており、現代では知性が軽視されているがゆえに、文化的な資質が失われており、人格的に薄っぺらくなったと論じる。
私利私欲に走る
明治から戦後にかけて、人々は勉強をして知識を得たいという向学心が高く、特に、戦後は、日本を復興させたいという目的もあり、向学心が高まり、世の中が一体となって社会をよくしようという雰囲気があった。その結果として、「一億総中流」社会が実現するほどの復興を遂げた。
こうした公のために尽くす精神をもっていた戦後に対して、バブル以降、自分の私利私欲のために行動することを恥じない精神が蔓延るようになっていった、と著者は述べる。
その原因が、伝統的に続いてきた「精神文化」・「身体文化」が、特にバブル期において、退廃したことにある、としている。バブル期に人々は、投機に夢中になり、「自分で汗をかくことなく不労所得を得る」ことに「血眼」になり、同時に、「古典的な教養が重視されなくなった代わりに、『サブカルチャー』がもて囃されるようになった」(p.46)、と著者は分析する。
本書では、必ずしも教養の軽視と精神的退廃の関係の必然性が論じられているわけではないように思えるが、たしかに教養とされる伝統的な文化が、人格の涵養や公のための精神を重視する点を鑑みると、両者には関係があるように思われる。
想像力が養われない
よく言われることではあるが、小説に比べて、アニメや映画などの動画は、想像力の働く余地がない。
実際、「活字を読んでいるときと、動画を観ているときとでは、脳の前頭葉の活性化の度合いがまったく違う」(p.93)という。
文学作品を読む体験は、読者が自らの頭を使って、文字情報から映像を想像・創造するという「最高度の知的活動」である。こういったことをしなくなれば、想像力が失われる。想像力が失われれば、知性も失われる、と著者はいう。なぜなら、「知性や想像力は不自由さを補うというところから出発するもの」であり、「想像力は知性の土台になる」(p. 96)からである。
遺伝子至上主義になる
現代は、「顔がいい」とか、「スタイルがいい」とかいった見た目の良し悪しに価値を見出す風潮が支配している。顔やスタイルといった身体的な特徴は、ほぼ遺伝によって決定される以上、こうした風潮は、「遺伝子至上主義」と呼べるのではないか、と著者は主張する。
このような遺伝的な要素に価値を見出すような価値観に囚われていることは、不幸である。なぜなら、遺伝的な要素は、生まれつき決定されており、それらを後天的に努力でどうにかすることは、ほとんど不可能だからだ。
自分の見た目という変えられないものに価値判断の基準を置くことは、遺伝子という先天的なものに価値の基準を置くことであり、自分のことを後天的な努力によって肯定できないような価値観をもつことである。確かにこれは、不幸な価値観といえるだろう。
これに対して、知性・教養は、後天的なものであると著者は言う。そして、それらを重視する価値観は、人間が後天的に努力を通じて、自らの価値を高めていけるような価値観である。つまり、後天的に自分自身を肯定できるような価値観なのである。
ここで、著者は平安時代の貴族社会が、「歌や手紙のやり取りを上手にこなせるだけの教養」が「モテ基準」(p.51)であったことを例に出し、教養が評価される時代が実際にあったと述べる。これは、単に自分を肯定するという目的のために知性を重んじる価値観を採用するのではなく、実際に、知性や教養が、人としての魅力であったということを示すための例示であろう。
人々は知的になれるのか?
以上のように、知的な生活はさまざまな良い点がある。
しかし、著者の言うように、知性や教養は本当に後天的なものといえるのか。本当は、それも遺伝によって決定されており、人が知的になれるか否かは、後天的な努力によってはどうにもならないのではないか、という疑問が生じるだろう。
つまり、人は、後天的に知的になれるのか、が問題になるのである。
著者は、本書の冒頭で、知的生活を「一部の専門的な職業の人だけができるものではありません。すべての方が実践できるものです(p.3)」と述べている。そして、『知的生活のすゝめ』と言うように、読者にも知的生活、つまり知性的・教養的であることを薦めているのだ。
であるならば、人が知的になれるということを証明し、その方法を説明する必要がある。
人は後天的に知的になれるか
著者はまず、人が後天的に知的になれることの証明として、非行少年たちの指導者の話を紹介する。指導者の話によると、少年院に入ってくる人たちの多くは、最初、「本を読むことができず」、漫画を読むときも「フキダシの中のセリフや説明は飛ばしてしまう」という。
しかし、そうした子どもたちでも粘り強く指導していると、だんだんと本の面白さに気づいて読めるようになり、日記も書けるようになって、やがては人間性そのものも変わっていく(中略)。(p.84)
このように、非行少年であっても、指導する人がいて、訓練・練習をしていくことで、徐々に本が読めるようになるのである。
同じような例として、著者は、死刑囚の永山則夫が、刑務所で読書をすることで、自らの罪を後悔し、自伝を書いた例を挙げている。
非行少年や死刑囚という知性的とは言い難い人々が、徐々に本を読んだり、日記や自伝といったまとまった文章を書けるようになるということは、多くの人が後天的に知性を身につけることが可能である、という根拠になりうるだろう。
知的になる方法
著者が例に出した非行少年や死刑囚が読書の習慣を身につけたのは、少年院や刑務所という閉鎖的な空間であった。そこでは、おそらく読書以外にすることが少なく、いわば読書をする強制力が働いていたといえる。
著者は、人を知性的にするには、そういった強制力のある環境が必要だという。しかし、一般的な人がまさか刑務所に入るわけにはいかない。では、どういった環境がいいのか。
まずは、同年代の人々からの刺激をもらえる環境が有益である、という。
たしかに、著者が言うように、教師や年長者が、自分よりも知識があるのは当たり前ともいえる。だが、同年代の人が自分より多くの知識・教養を身につけていると、自分も引け目を感じ、刺激になるだろう。
また、「知的圧力」が大事だという。
これは、「この程度の知識・教養があるのは当然だ」という周りの空気や、教師によるプレッシャーである。こうした圧力があることで、それを受ける人々の能力を発揮させてあげることにつながるのである。
著者は、「自主性に任せる」ことを、「若者たちのせっかくの能力をスポイルする恐れがある」(p.140)としている。
つまり、年長者が知的圧力としてのハードルを設定し、同年代の人々がそれをクリアしていくような環境に身を置くことで、人は知的になっていくのである、ということだ。
まとめ
著者は知的に生きることのメリットを、いままで知的に生きることを考えてこなかった人たちにもわかりやすいように説明している。より明るく、活力を得られ、幸福になれるというメリットは、誰にとってもわかりやすく、インセンティブとして機能しやすいだろう。
同時に、反知性的であることのデメリットを説明することを通じて、知的に生きることのより理論的なメリットを説明している。それは、人格的な成長であったり、社会的な意義である。
そして、知性的に生きることが、誰にでも可能であり、生まれに関係なく誰もを幸福にしうるものであるということが主張されている。これが本書の最も伝えたいことだろう。