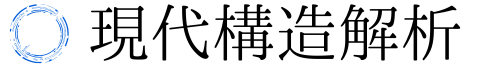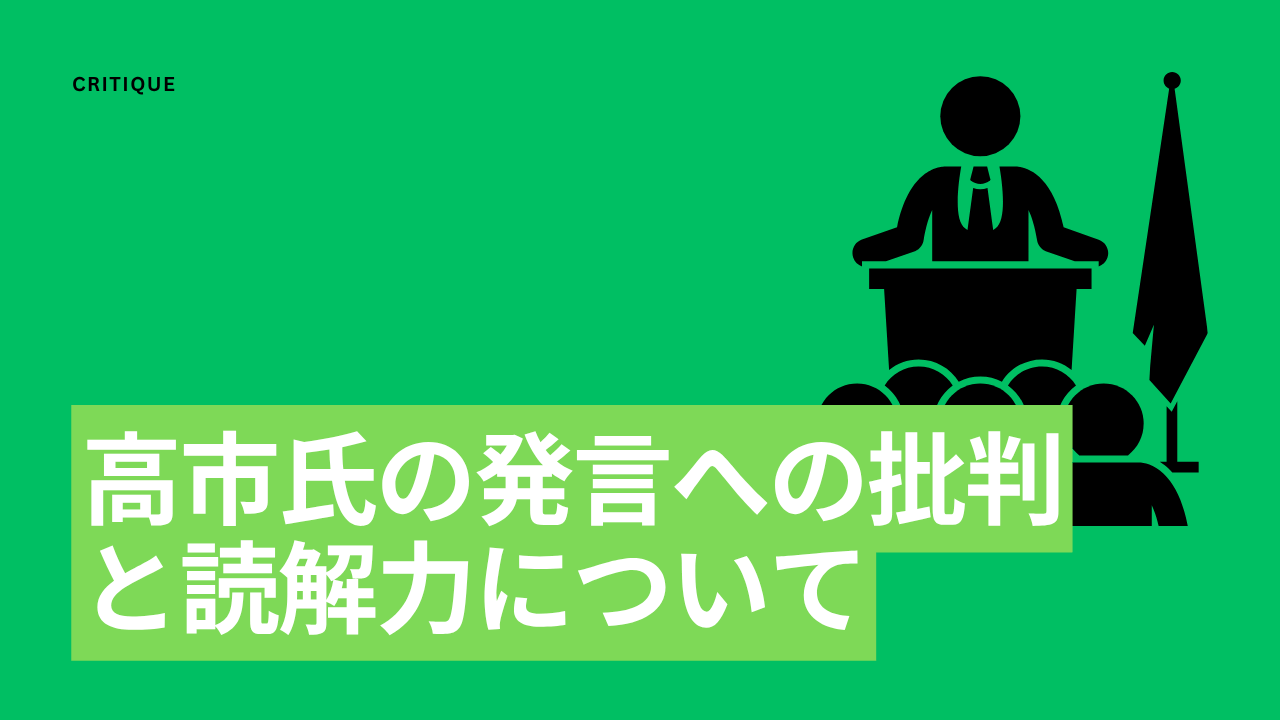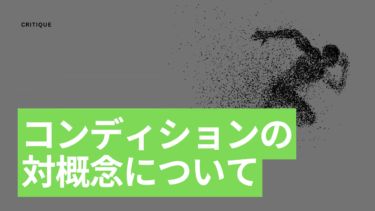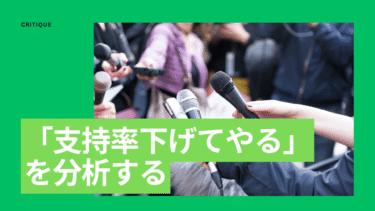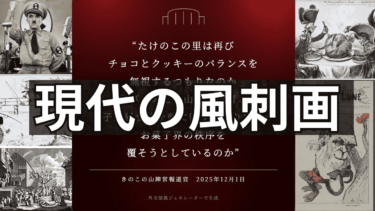先日、新しい自民党総裁に就任した高市早苗氏が、自民党議員の前での演説をした際の発言が、一部から批判を浴びた。
高市氏は、「全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます」「私自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます」という発言をした。[1]
これに対して、「ワークライフバランスを捨てるとは何事か」、「人間は馬ではない」、というような趣旨の批判をする政治家やメディアがいた。
昨今、このような的外れな批判は、今回に限らず、さまざまな場所で見られる。こういった的外れな批判がなぜ起きるのか、その構造について分析する。
高市氏への批判がなぜ的外れか
まず、高市氏への批判が的外れな理由を分析する。
高市氏が言った「ワークライフバランスを捨てる」「馬車馬のように働いてもらう」という言葉は、総裁就任時の演説で述べたものである。つまり、これからその職に就くにあたっての意気込みを述べたものである。
一般的に、その職に就くにあたっては、多少大袈裟な表現を用いて、意気込みや抱負を語るものである。たとえば、「粉骨砕身努力する」とか「身を粉にする」とかさまざまな言い回しがある。これらの言葉も、実際に身体を砕いたり、粉にするわけではないことは明白だ。
「ワークライフバランスを捨てる」とは、文脈から考えて、現代版のそういった言い回しであるということは、自明だろう。意味合いとしては、多少ワークライフバランスを無視してでも頑張るという意味で、そもそも、「身を粉にする」と同じく、実際に24時間仕事し続けることは不可能である。
また、自民党議員にあてた、「馬車馬のように働いてもらう」という言葉も、自分も頑張るし、議員たちにも頑張ってもらうという当たり前のことを言ったまでだろう。
そもそも政治家とは、自ら立候補して、国のために働くことを自分で選択した人である。それゆえに、政治家には労働基準法が適用されない。つまり、政治家は、本来、自らの意思で、ワークライフバランスを捨てる覚悟で働くという意思をもってなる職業なのである。
それに加え、現在、社会問題は山積し、その原因は、政治家に起因するところも大きい。
ゆえに、そんな状況下で、同じ立場の議員に対して、発破をかけ、共に努力をしようと呼びかけることは、むしろ当然であるといえる。
このように、文脈を考えれば、以上のような批判が的外れであることがわかる。
的外れな批判と読解力
このように、高市氏の発言に対する批判は的外れなのだが、このところ、この件に限らず、こういった見当外れな批判がみられることがしばしばある。
このような見当はずれな批判をする理由として、一般的に挙げられているのが、「読解能力の低さ」である。では、このような見当はずれな批判をしてしまう「読解能力の低さ」とは何なのか。二つのタイプに分けて考える。
①感情先行型
これは、SNSでよくみるタイプだ。
たとえば、ファミリーマートの「お母さん食堂」というネーミングが批判を受けたが、この批判は、このタイプの「読解力の低さ」による的外れな批判だった。
この批判の内容をまとめると、「料理は母親が作るものという考えが、固定観念で、男女差別的だ」、というものだった。
だが、言うまでもなく、「お母さん食堂」というネーミングは、「お母さんが作る料理のような商品」を意味しているのであり、「お母さんのみが、料理をするべき存在である」ということは意味していない。
つまり、そこには、論理的な飛躍がある。そして、その飛躍は、感情が先行することによってもたらされている。
この例の場合、そこにある感情は、おそらく被害者感情である。具体的には、「自分は、男女差別や男尊女卑にもとづいたジェンダーロールによって、被害を受けているのだ」、あるいは「女性が女性であるという理由で、低く見られているのだ」という被害者感情である。
この感情をもたざるをえないような社会的な不公正があるならば、それは是正すべきである。
だが、「私は被害を受けている」という意識が過剰になると、「お母さん食堂」のように、そういった意図はないのにも関わらず、何もかもが自分を加害するものであるかのように見えてしまう。
その構造は、以下のようなものである。
情報の受け手は、ある感情に支配されることで、あらゆるものを解釈する際に、その感情によって解釈が影響を受ける。
特に、「差別されている」というような強い感情は、強烈に解釈を歪める。結果として、自分のあらかじめ抱いていた感情に、解釈を合わせる形になる。この例でいえば、「差別されている」という感情に合わせて、「これも差別だ!」というように解釈を歪める。
したがって、情報の受け手が、ある感情に支配されていると、その感情が解釈を歪め、意味されていないことを受け取るのである。こういった間違った解釈が、第三者からみれば、「読解力の低さ」にみえるのである。
②結論先行型
今回の高市氏への批判はこのタイプである。
感情先行型が、意図せずに、自らの感情によって解釈を歪められてしまうのに対して、結論先行型は、ある結論に導きたいという動機のもと、解釈を恣意的に歪めるものである。
あるいは、ある思想に染まりきっているため、その思想に都合のいい解釈をすることが無自覚的に染み付いてしまっているということもあるかもしれない。
いずれにせよ、発言に対して、受け手のなかにそこにもっていきたい結論が先にあって、それに合わせるように発言の解釈を歪めるのである。つまり、自分の意図に合わせて、相手の発言を飛躍して解釈するのである。
読解力の本質とは
上記の「読解力のなさ」には、共通して、論理の飛躍がある。その飛躍が起きる理由に、二つの型があるということだ。
この論理の飛躍とは、相手の発言を、相手の意図しないような意味と結びつけることである。今回の高市氏の件でいえば、「ワークライフバランスを捨てる」という発言を、「世間に対してワークライフバランスを捨てるように強要している」というように、意図に反して結びつけている。
では、このような論理の飛躍をしないようにするためにはどうすればいいか。すなわち、読解力の本質とは何なのか。
文脈を捉える
まず、相手の発言を正しく読解するためには、文脈を捉える必要がある。
発言には必ず文脈がある。なぜなら、発言や文章とは、全体の流れのなかに位置を占め、全体として意味をもつからである。
今回の例でいえば、総裁就任の抱負を語るという文脈のなかで、発言を解釈しなけらばならない。たとえば、今回と似たような発言が、過労が問題となっている業界での講演であったら、全く別の意味をもち、問題となってもおかしくはない。
要するに、発言とは、その一文のみで意味をもつのではなく、発言全体や、その発言がされた舞台といったより大きな全体を文脈として考える必要があるのである。
こういった全体を無視した「切り取り」が炎上しやすいのも、こういった理由による。
相手の意図を汲み取る
そもそも、発言や文章は、どこまでいっても不完全で、誤解の可能性を拭いきれないものである。それは、考え方や背景が違う人間同士が行うものであるから、避けられないことである。
コミュニケーションとは、そういった違う人間同士が、何とかして思いを伝えようとする行為である。
そのため、伝える方は相手に伝わるように努力することは当然としても、聞き手の方も、相手の言っていることを理解しようと努力することは、同様に当然なのである。
そういった努力として、相手がどういう文脈で、どのような意図をもっているのかを察するべきだし、仮に、誤解を生む可能性がある表現があったとしても、相当の理由がなければ、相手への礼儀として、少なくとも表面上は、好意的に解釈すべきである。
たとえば、悪意があるという証拠がない限りは、相手からの褒め言葉を、皮肉として受け取るべきではない。
もっとも、「政治家である」ということは、その相当の理由になりうるといえるかもしれないが、少なくとも、解釈の可能性として示すにとどめるべきである。いずれにせよ、今回の高市氏の発言に対する批判は、どのように解釈しても的外れではあるが。
まとめ
昨今の社会では、感情先行型や結論先行型の解釈によって発言が歪められ、批判され、炎上することがよく見られる。
こういった的外れな解釈に惑わされないようにするためには、発信者の注意と同様に、聞き手のリテラシーも重要である。
聞き手が注意深く文脈や意図を捉えることができれば、的外れな解釈を一蹴できるからである。