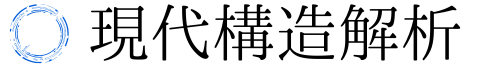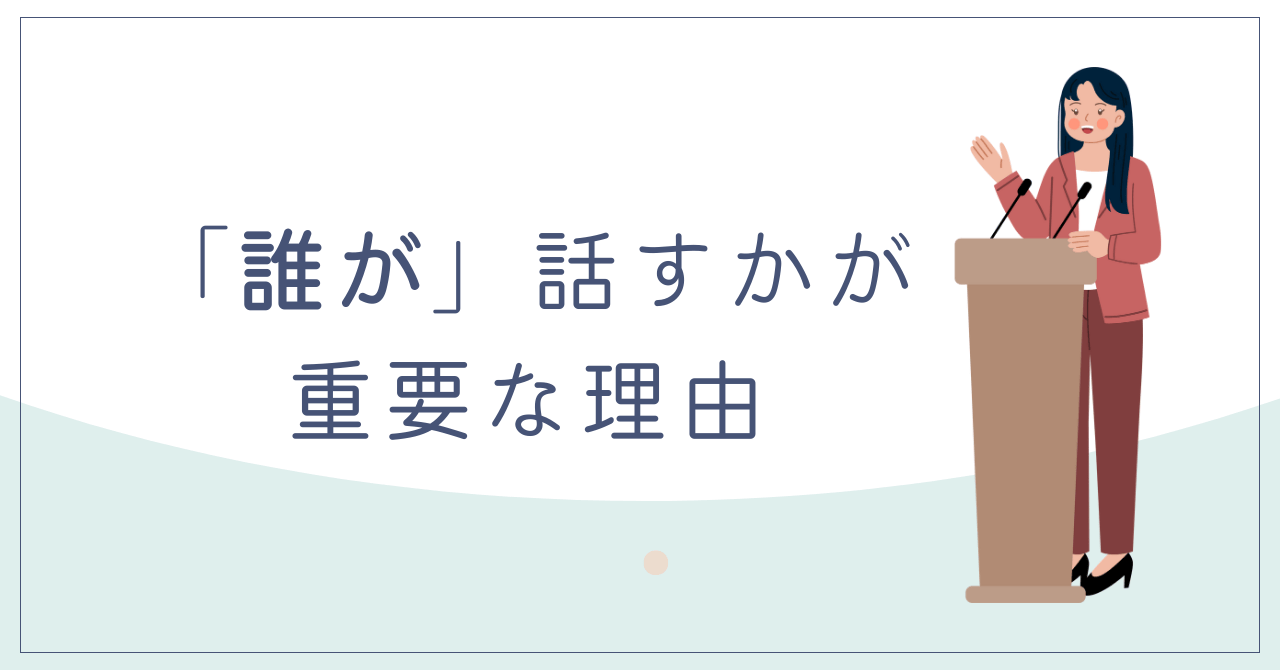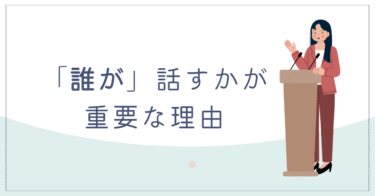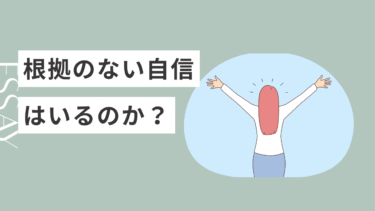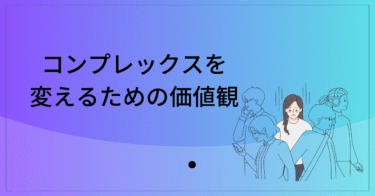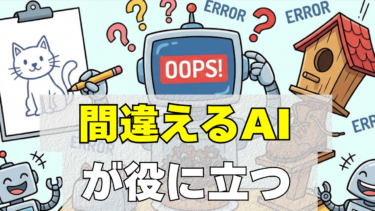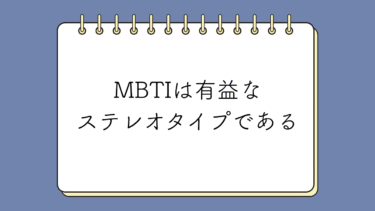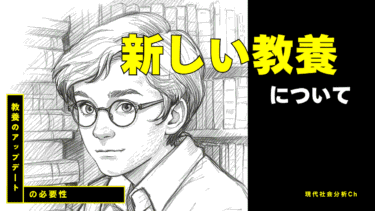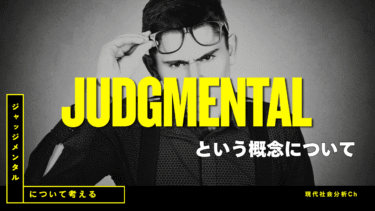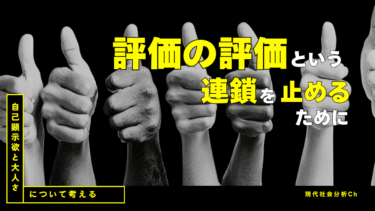何かを話すときに、「誰が言うのか」が大事であるとよく言われる。
それに対して、「誰」が言うのかは大事ではない。「何」を言うのかが大事である。「誰」が言うのかを重視することは、人によって言うことを聞いたり聞かなかったりするということで、それはよくないことだ、と言われたりもする。
今回は、話をする上で、なぜ「誰が言うのか」が極めて重要であるのかの理由を論じたいと思う。
論理的内容と感情的内容の違い
「誰が言うのか」と「何を言うのか」を言い換えると、話の話者と話の内容といえる。
もちろん、内容も大事ではある。どんなに立派な人が話をしたとしても、内容が全くないのでは、いい話とは言えない。
だが、話の内容だけが良くても、それだけでは、いい話にはならない。
たとえば、仮に全く同じ内容の戦争体験についての話を、戦争を実際に体験した人から聞くのと、実際には体験していない人から聞くのでは、全く異なる。体験していない人の話を、いい話ではないと言うつもりはないが、やはり、実際に体験した人の話と比べれば、その話の迫力や説得力が劣るのは事実だろう。
話の内容が同じならば、話の論理的な意味は、同じになるはずだ。だが、そうは感じない。それはなぜか。
その理由は、話には、論理的な内容と、感情的な内容の二つがあるからだ。
論理的な内容は、話の純粋な意味である。わかりやすく言えば、文字起こししたときの文章の内容といえるだろう。それに対して、感情的な内容は、その話の話者や内容全体から、聞き手に伝わる感情のことである。
この二つのうち、より人の心を動かしたり、人を本心から説得させるのは、大抵の場合、感情的な内容なのである。
なぜなら、人は話の内容の論理的な意味を理解して、その話について判断しているのではなく、その話全体から受ける感情的な印象に基づいて、その話について判断しているからだ。そして、その話について、それが感情的に正しいと思わないと納得できない。
これを的確に表した表現は、「腑に落ちる」だろう。腑に落ちるとは、腑=内臓に落ちるようにスッと納得することを表し、真の納得には、肉体的な感覚、すなわち納得感が大事なことを表している。つまり、納得とは、頭で考えてするものではなく、感覚的にするものなのである。となると、論理的な内容よりも感情的な内容の方が重要なことも頷ける。
理解と納得の違い
以上のように、話には論理的な内容と、感情的な内容がある。そして、人を説得し、納得させるのは、感情的な内容の方である。
論理的な内容は、感情的な内容に比べて、納得させる力が弱い。それを表す好例として、「頭では理解しているが、行動できない」というものがあるだろう。
たとえば、運動が健康に大事だと言われ、それを頭ではわかっていても、なかなか行動できない。これは、頭での理解が論理的な内容に基づくものであり、それでは心から納得し、行動に至ることはできないということを示している。
これが、たとえば、大病を患って健康の大事さを実感したり、運動によって健康増進を体感すれば、行動に移ることができるだろう。
つまり、頭で理解というのは、あまり力がない。少なくとも、面倒に感じる行為をとらせることはない。運動のような労力のかかる行為をするには、本当に心から身をもって納得しなければならないのである。
したがって、頭での理解と心や感覚での納得は全く質的に異なるのである。
なぜ誰が言うのかが大事なのか
したがって、論理的な内容は頭での理解をさせるにとどまり、聞き手を心から説得したり、納得させることはできない。本当に聞き手を説得や納得し、心を動かすことができるのは、感情的な内容である。つまり、相手を説得や納得させるためには、相手の感情を動かさなければならない。
何かを話すことで、相手の感情を動かし納得させるためには、まず自分が感情的に納得していなければならないだろう。
なぜなら、そうでなければ、本心から自分の感情を込めて話すことができないからだ。話者が本心から納得していれば、その人は、自然とそうした感情を込めることができるし、自然とそのような人生を送り、それが人柄に表れているはずだ。
わかりやすい例を出せば、運動の素晴らしさを話す場合、話者が本心から運動が素晴らしいと思っていれば、話に込められる熱量も高いだろうし、全体的に運動をしていそうな雰囲気がでているだろう。
また、本心から道徳心のある人なのか、単に綺麗事を言っているだけなのかは、その人の顔や人となり、所作を見れば、透けて見えるだろう。
このように、話者がまず話す内容について心から納得しており、それゆえに、それが話者に表れているという状態があるからこそ、話者が話す内容が真に説得力をもつのである。