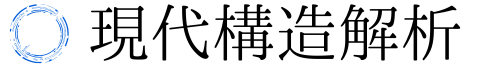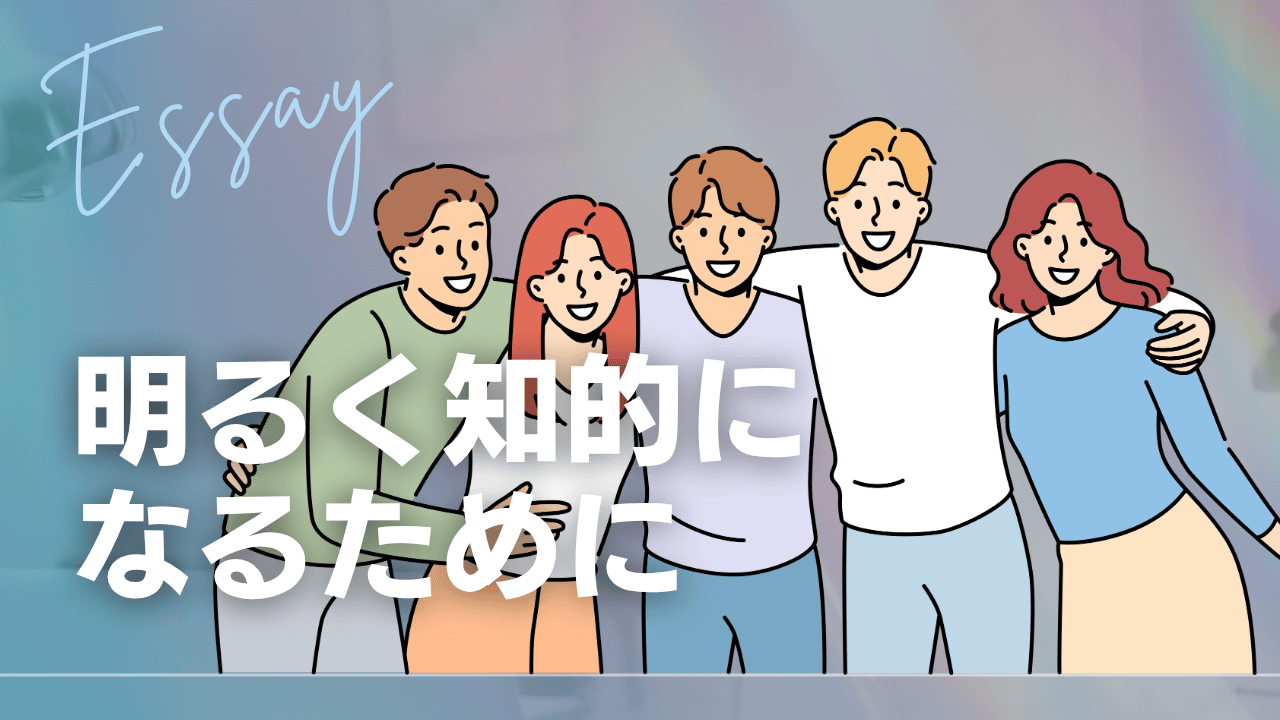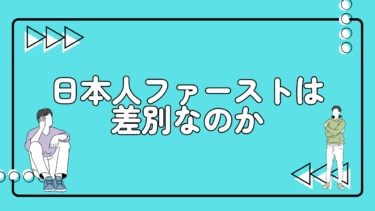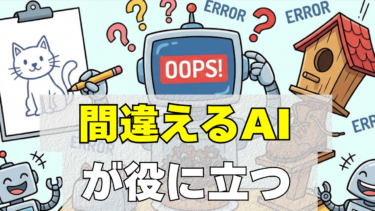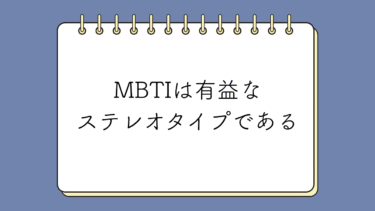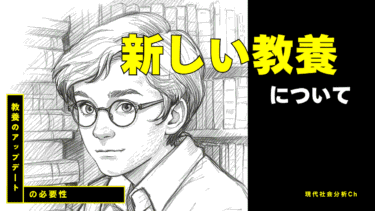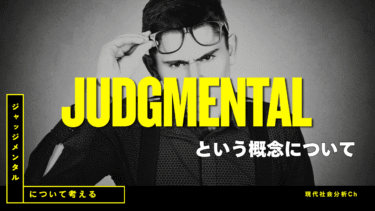多趣味である意義
水は溜まると腐る。流れがあるから、綺麗なままでいられる。
同じように人も、何かに囚われ、そこから抜け出せなくなると、澱んでいき、鬱屈する。そして、人格的には健全さを失い、腐っていく。
たとえば、勉強に取り憑かれたガリ勉は、大抵、性格も暗く、捻くれる。恋人に依存する人間は、メンヘラになる。楽しみのない主婦は、夫を憎むようになる。
ということは、人間が健全でいるためには、適度な開放性が必要なのである。開放性とは、他のものと関係を結ぶことに対して、オープンであるということだ。
典型的なのは、多趣味な人である。多趣味な人は、何をするにしても抵抗がなく、受け入れ、とにかくやってみる。色々なものに対して、楽しみを見出し、興味をもてる。こういう人であれば、多少の嫌なことがあっても、他に楽しみがあるから、気を紛らすこともできる。
人間関係でも同じだ。友人が多い人は、多少の人間関係の軋轢では動じない。これに対し、交友関係が狭いと、必然的に関係が重くなり、ドロドロしやすくなる。
開放的であると薄くなる
であれば、ものであれ人であれ、関係は多く持った方がいいのか。精神衛生上はそうだろう。
だが、多趣味の人がどれも中途半端になり、友人の多い人が深い付き合いを持ちにくいように、関係に開放的であると、自分の興味関心が分散し、深まっていかないということにもなる。
深まらないからこそ、澱まないし、ドロドロしないのだが、そのままでは、知識も、技術も、人間性も磨かれない。多くの関係が薄く、分散したまま、それが自分に統合され、血肉にはならない。要は、人間的に薄っぺらくなってしまう。
健全に深くなるために
①関係に核をもつ
何か一つのものだけに集中し、そればかりと関係すると、新しい風が吹き込まず、鬱屈する。かといって、次から次へと新しいものに手を出していると、刹那的で、中途半端になる。
とすれば、何かに集中しつつ、その周辺を探索するような遊び心があるといいだろう。
たとえば、あるアイドルグループのことが好きになったとして、そのグループの誰かだけにどんどん集中して好きになっていってしまい、他のメンバーや曲、あるいは他のグループを視界から外していってしまうと、歪んだ執着的な愛に発展しがちだろう。
そうではなく、あくまでもそのメンバーを興味の中心核にしつつ、そのメンバーとのつながりで、他のメンバーやグループ、楽曲などに関心を広げていく。
こうすれば、興味の中心を保ちつつ、他のことへの関心も深められる。そして、その他への関心が、中心の理解を深めるという一石二鳥になるのだ。
『思考の整理学』という本にも、一つのことだけを研究するよりも、関心を広げ、それを互いに結びつける研究の方が、実りのある研究になると書かれている。
また、芸人のタモリ氏も、「面白いことは周りにある。やる気のあるやつは中心しか見ないから面白くない」といった意味のことを言っている。
いずれにせよ、何かに真に精通するためには、その周辺にも関心をもてるような知的な余裕が必要なのだろう。
②関係に縛られない
中毒や依存は、自分ではコントロールできなくなった対象との関係のことだ。言うまでもなく、そういった関係は、精神的に良くない。
あくまでも、関係の最終的な主体は、自分であるべきなのだ。自分がまず最初にあって、その自分が他のものや人と関係を結んでいる。そして、それを肯定できる。こうでなければ、自分がその関係に縛られていることになる。
時に、熱中し、文字通り無我夢中になることもあるだろうが、そういった自分を同時に肯定できていなければならない。
まとめ
要するに、周りの存在に一喜一憂しないしなやかな強さ、あるいはゆとりが必要なのだ。そのための関係構築の方法について、この記事では考えてみた。言うは易し行うは難しだが、こういったことを整理しておくことは大事だろう。