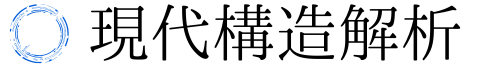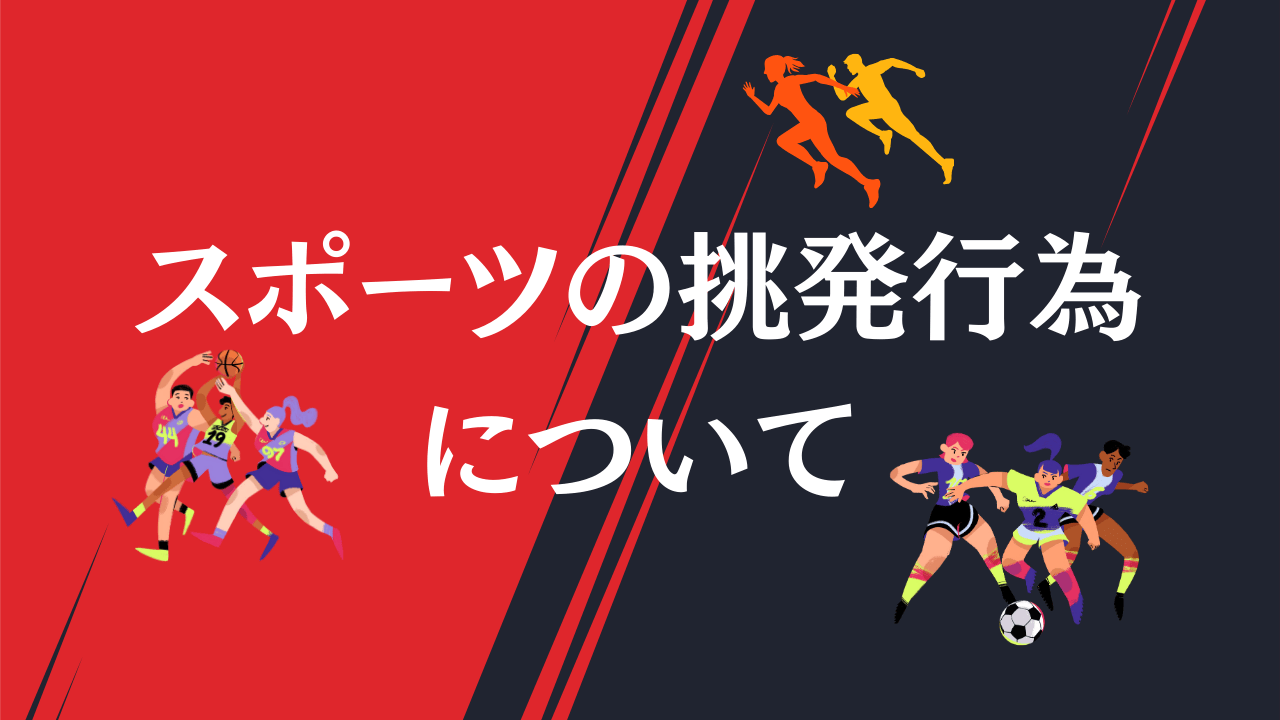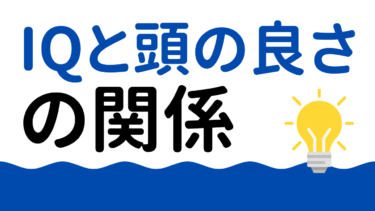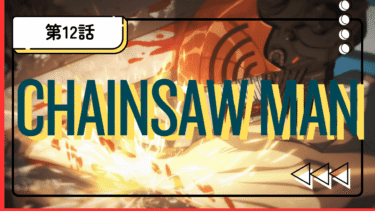スポーツにおいて、議論の絶えない問題がある。それは、挑発行為の是非である。
さまざまなスポーツで、リスペクトを重んじ、挑発行為などの非紳士的な行為を取り締まろうという動きがある。実際、そうした行為をした選手は、審判からのペナルティを受けたり、観客から非難を受けたりすることがある。
一方で、そういった取り締まりが厳しくなりすぎると、試合の盛り上がりに欠け、試合をつまらなくするという意見も根強い。
こうした、スポーツにおける挑発行為とリスペクトについて、その本質を考える。
スポーツにおける挑発行為
挑発的行為の禁止の例
まず、実際にさまざまな競技に存在するリスペクトを重視し、挑発的行為を禁止する例を挙げる。[1]
野球には、不文律や慣習が多い。そして、これに反した選手が、報復のためにわざとデッドボールを当てられることもある。
たとえば、最近、大谷翔平選手がやったことで話題になったが、ホームランを打った時に、バットを回転させるように放り投げる「バットフリップ」は、不文律的に禁止されていた。[2]
また、大差がついている試合で、3ボール0ストライクのとき、スイングをしてはいけないというものもある。これは、勝負が決しているのに、さらに点を決めようとすることが、いわゆる「死体蹴り」のようなものとみなされるからだろう。
これと同じようなものは、バスケットボールにも存在し、勝負が決しているときに、勝っているチームが点をとってはいけないという不文律がある。
卓球には、相手に1点も取らせないラブゲームで終わってはいけない、という不文律があるらしい。(批判もある)
これらの不文律は、ルールとして明示されていないが、多くの人が共有している点で、ほとんどルールのような具体性をもっているといえるだろう。
また、不文律のように、具体的な行為を禁ずるわけではないが、相手に対して、リスペクトに欠けるとされる行為が、警告を受けたり、相手の怒りを買うことはある。
相手に対するあからさまなガッツポーズやトラッシュトーク(相手に対して挑発的に話すこと)などがこれにあたるだろう。
挑発行為の禁止の見直し
総じて、こうした数々の不文律やリスペクトの原則は、対戦相手に対する挑発的行為を禁ずるものであるといえる。
だが、こういった挑発行為の禁止が、行き過ぎた禁止であるとして、見直され始めてもいる。野球のバットフリップや卓球のラブゲームの例がこれにあたる。
また、選手同士の煽り合いも試合の醍醐味だとするファンは多い。おそらくこの動きは、厳しくなりすぎたルール・不文律に反動するものでもあるだろう。
このように、スポーツにおいて、挑発行為の禁止と許容の間で、議論が起き続けているのである。
以下では、挑発行為に対する賛成意見と反対意見をまとめる。
挑発的行為への賛成意見
まず、挑発するような行為に賛成する意見を挙げる。
第一に、試合で戦っている以上、感情が高まり、それが表に出ることは、自然なことである。それを我慢して抑えることは、選手たちに無駄なストレスを与え、パフォーマンスを落とすことになりかねない。
あえて見どころを作るためにやるのではなく、エキサイトしていることを素直に表に出した方が、自分やチームを鼓舞することにもつながるだろう。
第二に、スポーツは、利益を目的とした興行である。そして、観客は、スポーツをエンタメとして見ている。そのため、見ていて面白くなければ意味がない。
確かに、試合を戦っている選手同士が、激しくやり合い、時に煽り合うくらいの方が、見ていて面白いだろう。
挑発的行為への反対意見
次に、挑発的行為への反対意見を挙げる。
第一に、スポーツの試合とは、相手がいなければできないものであり、その相手に対して、リスペクトがなければならないというものだ。これは、いわゆるスポーツマンシップである。
この考えの前提となっている考えは、スポーツの試合とは、戦争のような敵味方の殺し合いではなく、相手と自分で作り上げるものであり、相手の協力なくては成り立たないというものだろう。
第二に、スポーツの試合や選手が与える社会的な影響が大きいというものである。
これは特に、子供たちへの教育の面を考えてのことである。スポーツとその試合をする選手たちを見て育つ子供たちに対して、スポーツ選手の振る舞いは大きな影響を与えることは事実だろう。ゆえに、手本となるような振る舞いが理想ではある。
挑発行為への賛否の本質
以上の挑発行為の賛否の意見は、どれも理解できるものである。
だが、両者の議論は、本質的には噛み合っていないように思える。それは、スポーツの試合に対する考え方の違いであり、何を最も試合に求めるかの違いだろう。
そして、その求めるものの違いとは、どれだけ、「相手を負かすこと」に重きを置くかであろう。さらにいえば、どれだけ、対戦相手を「敵」として認識するかの違いだろう。
挑発行為に賛成する人は、スポーツの試合を、「相手に勝つこと」=「相手を負かすこと」が第一だと考えている。ゆえに、相手は、試合を作り上げる協力者というよりは、自分たちの「敵」として捉える。だからこそ、対戦相手に対して、リスペクトよりも敵対的な意識・感情が表に表れる。
これに対して、挑発行為に反対する人は、スポーツの試合を、相手に勝つことを目指しつつも、ことさら「相手を負かす」ことには重きを置いていない。
一番よくあるパターンは、相手を負かすのではなく、自分が良いパフォーマンスをすることで、試合に勝つことを目指すという考えだ。あるいは、スポーツとは、心身の鍛錬であるとか、楽しむためのものだと考え、勝ち負けは二の次とする人もいるだろう。
このように、挑発行為を認めるか否かは、相手を負かすことにどれだけこだわるか、言い換えれば、相手をどれだけ「敵」とみなすかによって決まるだろう。
スポーツの試合の本質とは
勝負への真剣さ
以上、挑発行為の賛否の違いが、スポーツの試合の見方、試合観の違いに基づくことを論じた。
では、そもそも、スポーツの試合の本質とは何なのか?
それは、試合である以上、勝負に対する真剣さであるといえるだろう。これはつまり、試合に全力で勝とうとすることである。
もちろん、試合の過程では、さまざまなものが得られる。実力が向上するだろうし、自分の精神力を鍛えることになるだろう。
だが、まず第一に相手に勝とうしなければ、手抜きであり、試合とは言えない。この勝負に対する真剣さが、試合の本質であるといっていいだろう。
ただ上記したように、そのための手段は、人によって異なる。相手を負かそうとするのか、それとも自分の力を出して勝とうとするのかである。
スポーツと攻撃性
この全力で勝とうとすること、その真剣さは、すなわち、全力で相手を負けさせることでもある。つまり、そこには、強い攻撃性がある。
そして、その攻撃性は、相手の存在そのものを脅かす攻撃性へと繋がりうる。その点で、試合とは、殺し合いや戦争との類似性があるといわざるをえない。
攻撃性を抑制するルールとスポーツマンシップ
しかし、このような勝負への真剣さがもつ攻撃性は、そのスポーツがもつルールによって制限を受ける。もちろん、相手を殴るような暴力行為は、ルール以前に違法ではあるが、そういった攻撃的な事態にエスカレートしないように、不必要な身体的接触を禁じるようなルールが定められている。そして、試合が終わったらノーサイドとなる。
つまり、試合とは、試合中には全力で試合に勝つために、相手に対して攻撃的にならざるを得ないが、同時に、ルールによって攻撃性を制限されれ、試合が終わった後には、即座に相手と握手をするのである。
こうしてみると、試合とは、かなり奇妙なものだといえる。なぜなら、試合においては、攻撃的になりつつ、ならないという大変困難なことが要求され、ある種の矛盾とさえいえるだろうからだ。
まとめ—相反するものの融合—
そもそも、相手に勝とうとすることと、相手にリスペクトをもとうとすることは、究極的には相容れない。
なぜならば、何が何でも勝とうとすれば、どんな手を使ってでも相手に勝とうとすることになるからだ。そこには、リスペクトが存在する余地はない。
だが、そうなると、それはスポーツではなく、戦争になってしまう。
確かに、スポーツが、人間の闘争心や攻撃性という戦争的な側面をもたないと主張することは困難だ。だが、スポーツにはルールがある。そして、そのルールの原理は、相手へのリスペクトである。
もちろん勝負において、エキサイトすれば、リスペクトに欠ける行為をすることがある。スポーツの試合とは、いわば興奮状態であり、それは当然のことである。ゆえに、そういった行為も、一定程度ならば許容されるべきだろう。
だが、ルールの原則はリスペクトにならざるを得ないだろう。なぜならば、スポーツが興奮状態を作り出すものだとしても、それは、社会的秩序の中で、制御された興奮状態だからである。いわば、スポーツとは、フィクションの戦争なのである。
攻撃性とその制御であれば、制御の方が優先されることは、社会のなかでは、ある意味当然だ。
とすれば、スポーツにおける挑発行為の是非や線引きを、最終的に判断するのは、社会的な価値観であり、社会がどの程度の秩序からの逸脱を許容できるかによるのだろう。
注釈
[1]野球:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%90%83%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%96%87%E5%BE%8B
バスケ:https://news.yahoo.co.jp/articles/30c47abfe7b29f0683d26abd300434dc02042d59?page=1
卓球:https://www.sanspo.com/article/20240220-PFVBRBM6MBPNBCHAOICWBKEL2M/
[2]最近では、見直されているようだ。参考記事