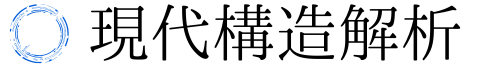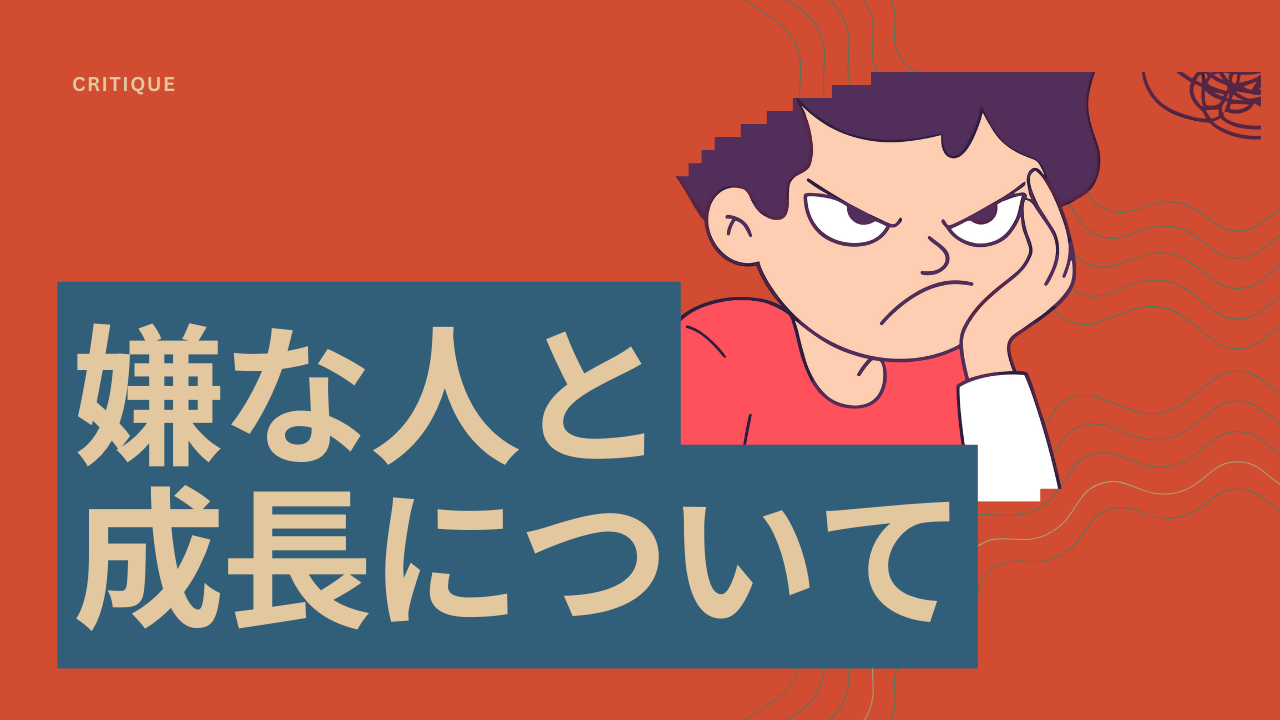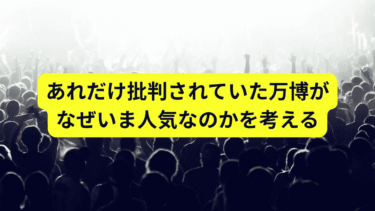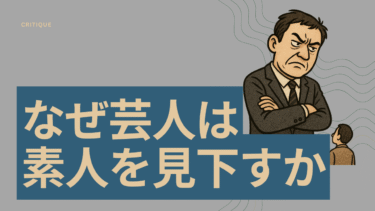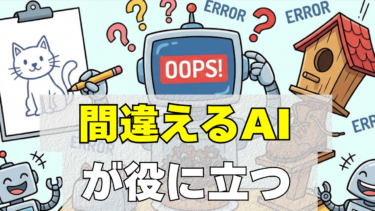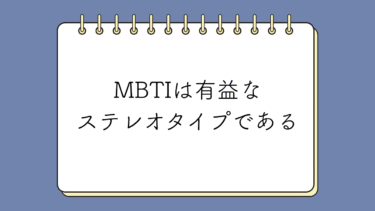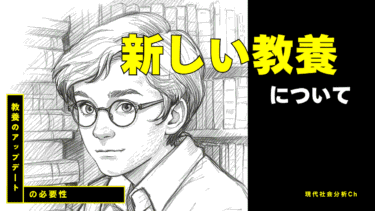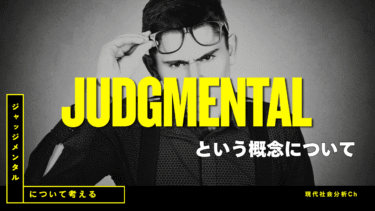人間、居心地のいいところにいては、成長しない。居心地の悪いところで挑戦してこそ、成長する。
このようなことを言う人は多い。確かに、その通りなところもあるだろう。
この言葉における居心地の悪さとは、主にハードな環境、特に要求の高い環境を指しているのだろうが、これは、人間関係についても当てはまると思う。つまり、嫌な人との関係が、自分を成長させることもあるのではないか、と思う。
そこで、自分にとって嫌な人との関係と、自分の成長について考える。
人の分類
まず、嫌な人とは何か。
世の中には、色々な人がいる。その色々な人を、それぞれの属性でまとめることは難しい。
だが、それらの人が「自分にとってどういう存在か」という観点から分類すれば、いくつかのタイプでまとめられるだろう。それを図にすると、以下のようになるだろう。
| 道徳的な善悪 | 個人的な好み |
| 良い人 | 気が合う人 |
| 悪い人 | 気が合わない人 |
ここでいう良い・悪いというのは、道徳的・客観的なその人の善悪で、気が合う・合わないは、個人的な相性といっていい。
分類の結果として、良い人で、かつ、気が合う人は、好きな人になる。
そして、それ以外の、いい人かつ合わない人、悪い人は、嫌な人になるだろう。
味方との関係
人は、良い人で気が合う人と、付き合うものだ。
そういった人とは、表面的な付き合いではなく、個人的な深い付き合いをする。この付き合い・関係を、友達や仲間と呼ぶ。つまり、自分にとっての味方である、ということだ。
この味方の存在は、言うまでもなく重要だ。なぜなら、そういった人とは、心からのつながりをもてるからだ。こうした人との関係が、自分の人生を豊かにする。
味方と現状維持
味方は重要な存在だ。自分にとって、他の人よりも、大事な存在である。だが、味方とだけ関係をもっていると、その関係が快適であるがゆえに、現状維持になってしまい、成長の機会が少なくなることになりうる。
確かに、味方であっても、時に、厳しいアドバイスがあって、それが成長につながることもある。だが、関係そのものは快適であるので、精神的に不愉快な状況は生じにくいだろう。
たとえば、嫌な人間にどう対処するのかとか、どのように敵対的な人間から自分の利益を守るのかといった状況は、嫌な相手でないと発生しない。
つまり、こうした、自分にとって不快で不愉快な状況は、味方でない人との関係からのみ生まれるのである。
嫌な人の道具的な価値
自分の味方からは得られないこのような成長の機会を、嫌な人(=悪い・合わない人)は与えてくれる可能性がある。つまり、嫌な人は、役に立つことがあるのである。
となると、先ほどの分類にもう一つの項目を足すことができる。
| 道徳的な善悪 | 個人的な好み | 道具的な価値 |
| 良い人 | 気が合う人 | 役にたつ |
| 悪い人 | 気が合わない人 | 役に立たない |
それは、役に立つか、立たないかという道具的な価値だ。
この役立つか否かという価値は、味方には当てはめる必要がない。そもそも、味方とは、役に立つか否かではなく、精神的なつながりによるものだからだ。
つまり、道具的な価値で判断する対象は、嫌な人である。そして、役に立つかどうかは、自分の見方次第であり、大抵の場合、役立たせようとすれば、役にたつのである。
たとえば、嫌な人と会話をするにしても、自分にとってのメンタルトレーニングだと思えば、役に立つといえる。
このように、人を役立つか否かでみることは、人を道具扱いしており、失礼だ、と思うかもしれないが、その相手が嫌な人であれば、それ相応の理由があるのであり、気を遣う必要もないだろう。
嫌な人は自分を成長させる
嫌な人というのは、自分にとって嫌な状況を作ってくれる。それは、不愉快でストレスのかかる状況である。
不愉快でストレスのかかる状況とは、すなわち居心地の悪い環境ということであり、それは、成長を促す環境でもある。
なぜなら、どうにかして、そこから抜け出そう=現状を否定するというきっかけを与えてくれるからである。
ゆえに、こういった状況・環境を作ってくれる嫌な人の存在は、実はありがたいのである。
まとめ
心の良い人、気の合う人は、自分にとって大事な存在である。人生は、そうした人たちと多くの時間を過ごすべきである。
だが、多少は、嫌な人にも時間を使ったほうがいいだろう。なぜなら、それが、自分にとって成長につながるかもしれないからだ。
カントは、「人を手段としてのみ扱ってはならない」と言ったが、それは、相手に道徳的な人格があることが前提となっている。道徳的な人格がなければ、手段としてのみ扱われる。それが、道具である。
人をどの程度手段として扱うのかは、相手の道徳心と自分の価値観によるのだろう。