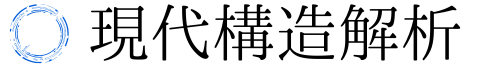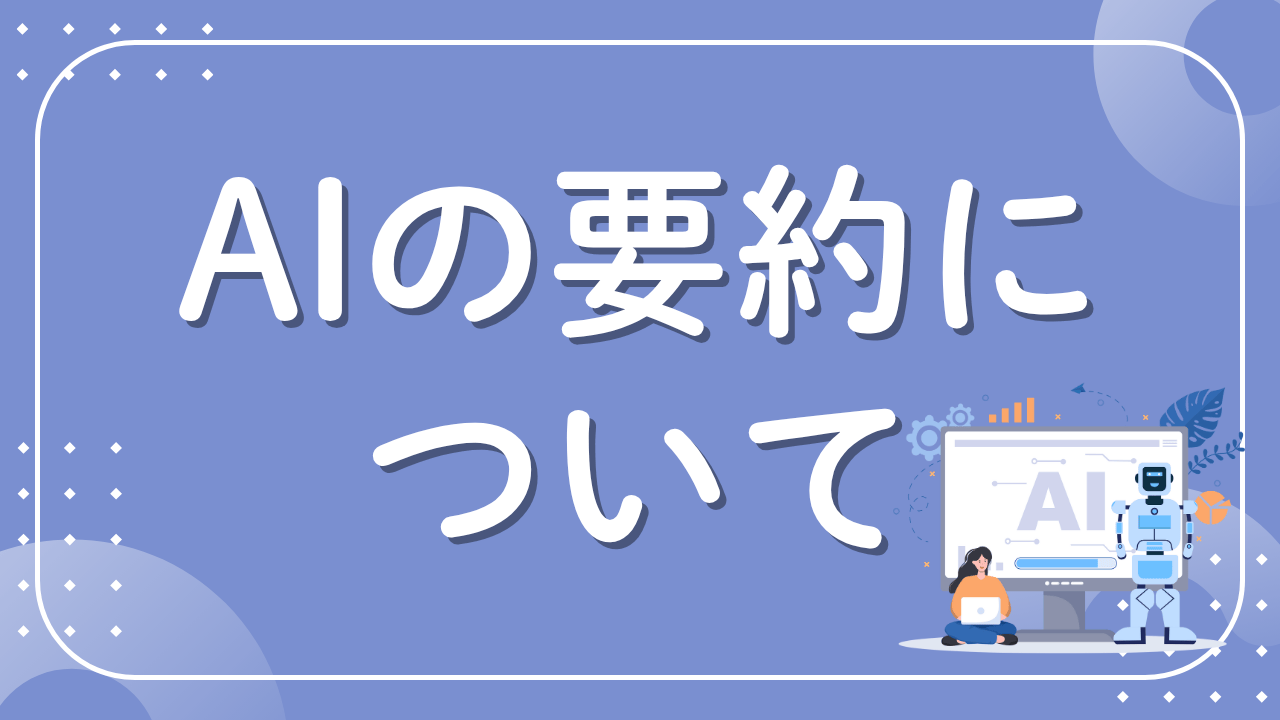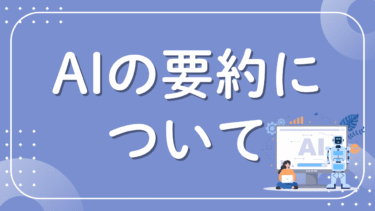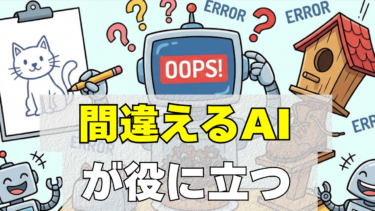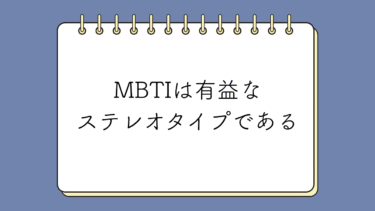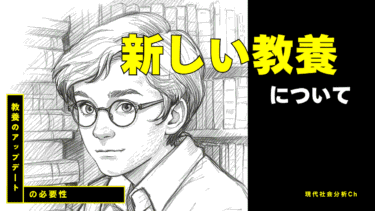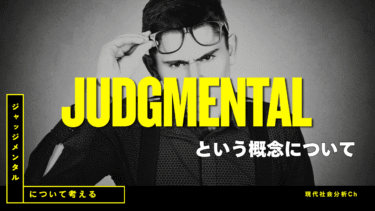昨今、AIの能力の進化が凄まじい。すでに汎用AIとして、様々な分野に使われているが、特に身近な利用例は、要約機能だろう。Webサイトから、PDFから、動画に至るまで、あらゆるものを要約して、まとめてくれる。非常に便利なツールである。
だが同時に、次のような疑問も生じる。
・なぜ、長い情報を短くまとめるとわかりやすくなるのか。
・短くまとめることで、削られ、失われるものは何なのか。これは、特に、文学作品が要約に不向きだと言われることと関係しているだろう。
・要約をAIにやってもらうことで人間の能力は衰えるのか、衰えるとしたらどんな能力か。
こういったことを、考えていく。
なぜ文章を要約したいか
そもそもなぜ、AIを用いて文章を要約したいのか。要約=短縮と考えるなら、なぜ文章を短縮したいのか。
それは、長い文章を読むのは面倒で、わかりにくいからである。それに対し、短くまとまった文章は、理解しやすい、と思われるからだ。
なぜ長い文章を読むのは面倒なのか
では、なぜ長い文章を読むことは面倒なのか。
①文章を読むことが面倒
そもそも、文章を読むこと自体、面倒な作業である。好きでもない長い文章を読みたいと思う人は、まずいない。
文章を読むとは、目で文字を追って、文の意味を理解し、文章全体での言いたいことを理解することであり、この作業自体が、頭を使うことであり、面倒なことである。
②いらない情報が多い
必要があって文章を読む場合、基本的には、何か知りたいことがあって、それを知るという目的がある。
だが、長い文章は、知りたいことに対して、情報量が多い。そのため、読み手の目的からすれば、いらない情報がほとんどなのである。そのため、宝探しのように、長い文章から知りたい情報を探さなければならない。また、どれが必要な情報かは、読んでみないとわからないため、安易に読み飛ばすこともできない。
このように、知りたい情報を知るために、必要のない情報の中から、情報を取り出すことは面倒である。
③情報が整理されていない
長い文章は、その長さに応じて、情報量や、主張したいことが増えていく。それに伴って、それらを補助するような文章も増えていく。つまり、文章は長くなるほど、どんどん複雑な構造になっていく。
構造が複雑になればなるほど、それらを理解しやすい形に整理することが難しくなる。それは、ちょうど部屋にものが増えるほど、整理が難しくなるのと同じである。
ということは、長い文章は理解しやすい形に整理することが難しく、必然的に、理解しにくいものが多くなると予想される。
長い上に、理解しにくいのでは、読むのが面倒なのは当然である。
このような原因から、長い文章を読むことは面倒だということになる。
要約とは何なのか
以上のことから、要約とは何かを結論づけることができる。
それは、
①読むのが面倒でないようになるべく短くする
②必要な情報のみを抽出できるようにする
③短くわかりやすく整理する
これが要約であるといえる。
要約によって失われるもの
要約は、短く、わかりやすく、整理するものである。
つまり、要約では、文章の本筋の論点のみを抽出することになる。結果、以下のものは、失われる。
①詳細な説明
要約の場合、結論がメインとなる。なぜその結論へと至るのかについての説明は、簡素化されるだろう。
たとえば、学術的な要素を含む文章であれば、ある結論を導くために、複雑な論証のプロセスがある場合が多い。こういったプロセスを省くことで、手っ取り早く結論を得ることはできるが、その分野に関する知識を深めるには、そういったプロセスも理解する必要があるだろう。
②過程
特に物語のような出来事が連鎖していくような文章において、過程は重要である。
たとえば、桃太郎を要約した場合、「桃から生まれた桃太郎が、おじいちゃんとおばあちゃんに育てられ、大きくなり、動物たちを家来に連れて、鬼を倒した」というようになる。
これでは面白くない。なぜなら、物語、あるいは文学は、その一つ一つの過程の方が、結論よりも大事だからである。
主人公が、様々な出会いをし、葛藤を重ね、挫けそうになっても、仲間の助けを借りて、敵を倒す。このような構成は、物語の典型だが、この構成だけ読んでも、何も面白くない。誰にあって、どんな葛藤をして、どういうときに諦めそうになって、といったような具体的で血の通った描写が、物語には求められるのである。この過程をいかに詳細に、鮮やかに描くかに、作家の力量が求められるのである。
したがって、物語や文学は、基本的には要約に適さないし、その理由は、過程=具体性を省くからである。
③回り道
要約は話の本線しか論じない。学術的な文章であれば、そもそも本線しかないため、問題はない。だが、物語やエッセイなど、必ずしも厳密な論理性が求められるわけではない文章の場合、話が飛躍したり、脱線したりすることが面白みであることも多い。
こういった文章を要約してしまうと、そのような独特の軽やかな面白みが失われてしまう。いわば、ぶらぶらと散歩がしたいのに、最短距離を歩かされるようなものである。
したがって、回り道が面白い文章を要約することはできない。
AIの要約に頼ることで失われる能力
AIに限らず、便利なものに頼ると、その分の能力は失われがちである。使わない能力は落ちるからだ。
では、AIの要約に頼ることで、落ちると懸念される能力は何か。
①読解力
読解力とは曖昧な言葉だが、上記の説明を使えば、わかりやすく定義できる。
それは、「文章を理解しやすい形に変え、不要な情報を削り、必要な情報を取ってくること」といえる。
この「理解しやすい形」や「不要・必要な情報」とは、人によって異なるだろうが、この定義自体は誰にでも当てはまるだろう。
この作業をAIが肩代わりすると、読解力が落ちる可能性がある。
常にAIを使えば困らないだろうと思うかもしれないが、読解力は、文章を理解する能力に限定されるのではない。要は、情報整理能力であるため、人と会話するときや、自分のなかで考えや思いをまとめたり、アイデアを出すときにも使っている。
こうしたことまですべてAI任せにすることは、人間が人間であるために、やめた方がいいと思う。
②相手を理解する力
これは、より細分化した読解力である。
相手の主張や気持ちを、自分にとって理解できる形に変える能力が落ちれば、相手のことが理解できなくなる、あるいは理解しようとしなくなる。
③捨てる力
これも、同様に細分化した読解力である。
情報過多の時代と言われる現代において、その情報を取捨選択し、「捨てる力」が必要だ、ということが主張されている。[1]
情報が多く、選択肢も多いなかで、自分にとって必要なものを見極め、取捨選択する能力は、重要であろう。
④独自の観点を作る力
要約を試験で行う場合は、中立的で客観的なものが求められる。だが、個人的に行う場合には、上記したように、その削り方も整理の仕方も個人によって異なるため、独自のものになる。
どこが重要だと思うのか、どこに強い印象を受けたのか、どうすればそれらをわかりやすく理解しやすい形にできるか。
要約を行う上でのこうした作業は、そのまま、独自のインプットとアウトプットを作る作業でもある。つまり、自分で文章を読んで、自分で要約することは、そのまま独自の観点を作ることにつながっているのである。これはすなわち、世界に対して、独自性、個性をもつこと、といえるだろう。
これをAIに肩代わりさせてしまうと、客観的で、個人の視点のない要約になってしまう。もちろん客観性・中立性が求められる場面は多くあるが、全てをそうしてしまうと、独自の観点を作る機会を失うことになる。
⑤忍耐力
これは、精神論的な主張になるが、長文を読むことは、忍耐力を養うことになる。
なぜなら、自分にとって必要な情報がいつ現れるかわからない、あるいは現れないかもしれないなか、文章を読み続け、それを自分の頭で整理し続ける作業だからである。
いわゆる知的な体力、持久力も身に付くことだろう。
こうしたことを経ずに、即座に知りたいことを知ることに慣れると、自分の知りたいことを徹底的に調べる、すなわち時間をかけてじっくりと調べるという知的探究心が衰えることにつながるかもしれない。
あるいは、簡易な感動、カタルシスを求め、長編の物語や映画を楽しむことができなくなるかもしれない。
まとめ
要約とは、長い文章を、不要なところを削り、整理することである。
それは、結論を手早く知りたい場合には適しているが、論証や結末に至る過程や回り道を楽しむ場合には適さない。
そして、AIに要約を任せることで、読解力や忍耐力が落ちる可能性がある。
とはいえ、便利であるので、やりたくないがやらなきゃいけないことに対してはAIを使い、その他は、時には自分で長文を読んでみるといいのではないかと思う。