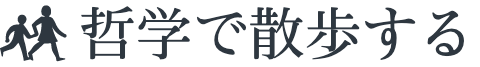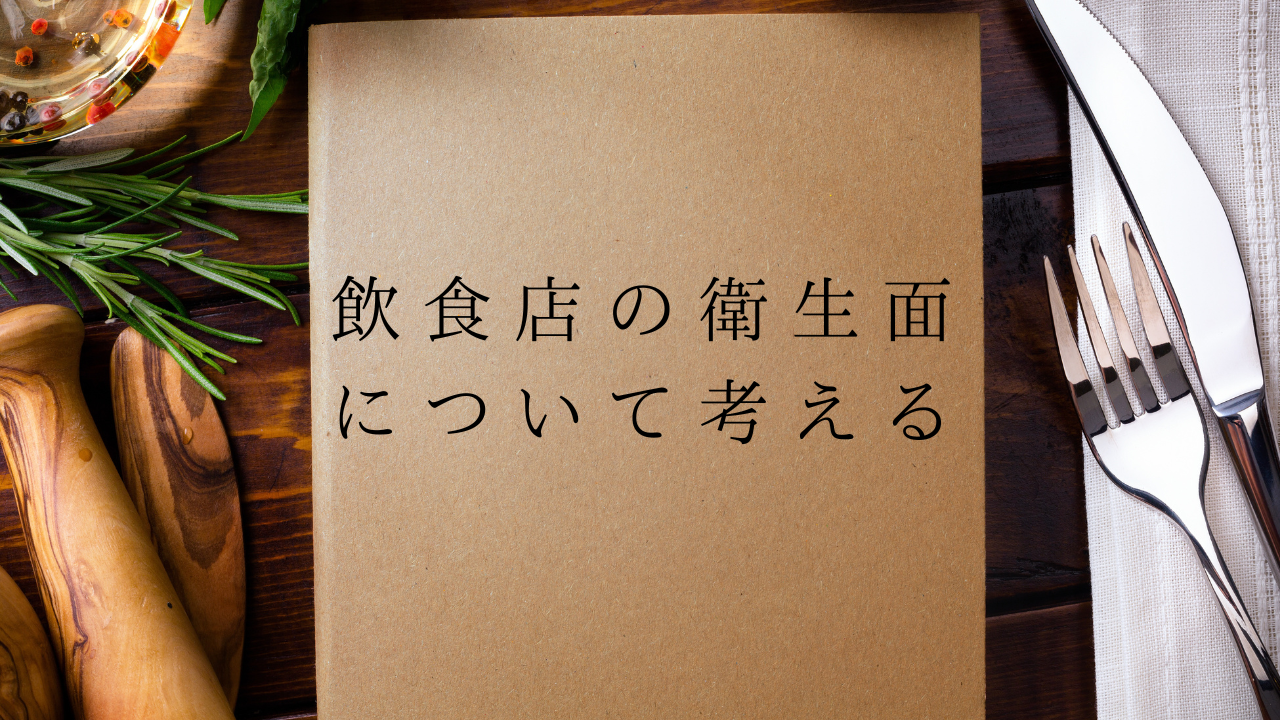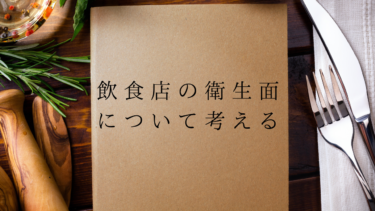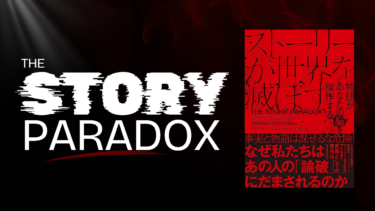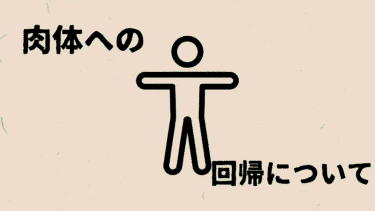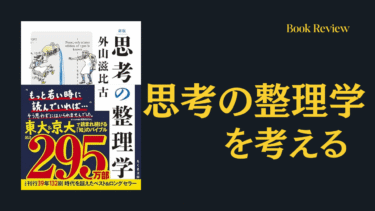先日、とある飲食店に行ったところ、出された取り皿が、洗い残しと油で汚れているようだった。結局、その取り皿を取り替えてもらい、その後、問題はなかった。だが、こういったことがあると、その店の衛生管理を疑問視してしまう。
社会全体でみても、飲食店での食中毒や、不衛生な管理体制は、度々ニュースにも取り上げられているが、こうした経験やニュースがあると、飲食店が信用が信用できなくなり、安心して外食ができなくなるだろう。
私自身、飲食店で働いた経験があるが、そのときに、飲食店は想像以上に、衛生上の問題が生じやすい構造であると思った。その原因は、店員に食品衛生のかなりの自由度があるからだ。自由度があるとは、衛生対策をやるかどうかは、基本的に店員の自主性に任されているということだ。
もちろん、衛生面での指導は受けるし、マニュアルが存在する店も多いだろうが、実際にそれがオペレーションとして守られているかは別の問題だ。とくに、細かな衛生管理は、店の管理者の目が行き届かないことが多い。実際、監視下になければ、決められた衛生管理をしなくても、特にペナルティなどはないことは多いだろう。つまり、店員の善意に任されているのだ。
もちろん、私を含めた店員は、衛生管理をきっちりと行なっていた。しかし、たとえば、店が忙しいときにも完璧に守られるか、優先度の高くない細かな管理をしっかりできるのか、こういったことはおろそかになりがちだろう。
そこで、今回は、飲食店が信用できない根本的な原因をまず考え、その原因をもとに対策と、信用できる店・できない店の見分け方を書いていく。
衛生的な問題の根本的な原因
属人的な衛生管理
そもそもの衛生的リスクの原因は、店員に対策を任せていることにある。人が食品などに触れている以上、ヒューマンエラーは発生しうる。極論すれば、すべてを機械による自動化におきかえれば、店員の不注意や怠慢による衛生上のリスクはなくすことができる。
監視とペナルティの不足
店員の怠慢による衛生上のリスクは、その店員に対する監視とペナルティによって減るだろう。しかし、現実には、人手不足や技術的な不足が原因で、店員の行動を監視することも、それに対してペナルティを与えることもできない。
それどころか、店員に問題があると分かっていながら、人手不足の影響で、その人をクビにすると店が回らないから目をつぶっているというケースも大いにありえるだろう。
店の利害と店員の利害の不一致
店員は基本的に、給料を稼ぐために仕事をしている。そして、同じ給料を稼げるならば、少しでも労力を減らした方が合理的である。つまり、店や客のことを考え、必要以上の労力を払うインセンティブが薄いのである。要するに、店の利害と店員の利害は不一致なのだ。
このことは、特にアルバイトに当てはまる。社員であれば、少なくない給料と、雇用をもらっているわけだから、その店の経営状態に多少なりともコミットすることになる。だが、アルバイトは、その店で働く目的が、時給を稼ぐ手段であることが多いため、彼らがその店の売り上げや信用に対する責任をもつことは困難だろう。社会的にも、アルバイトに対して、深いコミットを要求することはできないという雰囲気があるだろう。
まとめ
要するに、原因は、店員が労力を払い注意するインセンティブがないこと、そして、その店員に衛生管理の自由があること、である。
衛生的問題の解決法
以上の原因から、解決策は以下の2つになる。
1、店員に衛生管理の自由を与えない
2、店員に衛生管理を徹底する動機を与える
要するに、店員を物理的にコントロールするか、精神的にコントロールするかのどちらかである。
店員に自由を与えない
この解決策は、店員の自由な裁量をなくす、あるいは可能な限り減らし、物理的に衛生リスクを減らす方法である。ある意味、性悪説的な方法といえるだろう。
メリット
この方法のメリットは、何といっても物理的にリスクを減らせることだ。人間の意思という不確定要素を排除するため、確実に効果がある。
デメリット
具体的な実現方法に乏しい。たとえば、機械化するとしても、コストがかかるし、現状すべてを機械化することはできない。
また、この方法だと、店員の自由を制限することになる。これは、リスクを減らすことはできるが、店員のモチベーションを下げることにつながる可能性がある。そうなると、結局、店員はより衛生的なリスク要因となるし、客の体験も下がるだろう。
そして、この方法を突き詰めると、完全に人を排除することに行き着く。これが果たして、客に対して有益なのかはわからない。
店員に動機を与える
この解決策は、店員に衛生管理をしてもらうための動機づけを行う。動機づけの方法としては、インセンティブとペナルティの2通りがありえるだろう。すなわち、飴と鞭だ。
ただ、衛生管理を行うインセンティブをつけることは難しいだろう。そもそも、基本的に衛生管理は、行わなくてはならない。必須ではないが、やった方がいい衛生管理もありはするが、そもそもそれを把握し、評価することは難しい。
となると、ペナルティによって動機づけを行うほうが合理的だろう。ペナルティによる場合も、把握が難しくはある。ただ、店員の行動の全てを把握できないとしても、何か衛生管理の基準に違反している行為を発見したときに、ペナルティを与えることで、店員の行動全てに対して抑止力を働かせることができる。
この方法を採る場合、店員には常に監視されているという感覚を与えることが有効である。
メリット
小コストであり、実現可能である。人に頼らざるをえない作業が多いため、人の内面をコントロールすることは、効率がいい。
デメリット
店員に対して、常に監視されている感覚を与えるため、精神的に負担になる。あまり、厳しいペナルティを科すと、人が離れる可能性がある。
まとめ
これらの二つの方法は、権力による統治の方法と重なる。特に、フーコーの権力論である、規律訓練と生政治を念頭に置いている。(くわしくは、別の記事で論じる)
信用できる店・できない店の見分け方
以上のことを踏まえて、店の見分け方の基準を考える。
人の介入が多いか
これは、店員に自由を与えないパターンである。
人の介入を減らすということは、店員に衛生的な管理をさせないことであり、物理的に衛生的リスクを下げられる。たとえば、調理や洗浄などで自動化がなされている場合だ。
現状、調理を部分的に自動化する機械を導入している店はあるだろうが、完全に人の手を離れている店は、ほぼないだろう。ただ、調理工程においては、工場で冷凍し配送するような店や、ごく単純な調理しかしない店はある。そちらのほうが人の手の介入が少ないといえるだろう。
食器洗浄においては、ほとんど全ての店で、食器洗浄機が導入されているはずだ。洗浄機を使えば、よほどのことがない限り、食器が不衛生になることはないだろう。
この点からすると、ファミレスのように、工場であらかじめ調理をしてあるものを店内で温めるだけという方式の店は、人の介入が少なくより衛生的に信用できるだろう。ただし、それは調理工程に限るため、盛り付けや配膳、あるいは食品の店内での管理には人の手が必要であるため、総合的に信用することはできないだろう。
管理者が働いているか
これは、店員に動機を与えるパターンである。
オーナーや店長などの管理者、すなわち、自分の利益と店の評判が直結する人間がメインで働いている場合、その人物が衛生管理を怠る可能性は低い。仮に問題を起こせば、自分の生活に直接響くからである。
また、管理者が常に働いていることで、他の店員は管理者の監視下にあるため、衛生管理を怠りにくいだろう。
ただし、必ず管理者の目が届かない場所があるため、絶対とはいえない。万全を期すのであれば、すべての箇所にカメラを設置し、チェックできる体制を整える必要があるが、ここまでやる店は多くないだろう。店内から厨房内を見て、カメラなどの監視体制がある場合は、信用できる可能性が上がるだろう。
店内で店員同士がしゃべっているか
これは、店員に動機を与えるパターンである。
基本的に、店員同士の仲がいいと、店の管理は杜撰になる。なぜなら、店員の共通の利益は、「いかに楽に時間を経過させるか」であるからである。その利益を共有する店員が連帯すると、よりその利益を追求するようになる。経験から考えても、やらされている仕事を一緒に行う集団が仲が良い場合、より丁寧にやろうという方向には行きづらいのがわかるだろう。もちろん、全員のモラルが高ければ別だが、それは稀なケースだ。
また、店内で店員が仲良さそうにしゃべっている場合、その店の管理者が厳しくないことがわかる。厳格な管理者である場合、そのようなおしゃべりはできないからである。
したがって、店員同士が仲良さそうにしゃべっている場合、店員同士がサボりを助長し合う上に、管理者も厳しく指導していないということであるため、信用できない可能性が高い。
マニュアルに従順である
これは、店員に動機を与えるパターンである。
店員の行動がマニュアルに従順である場合、店員の自由度が少なく、マニュアルから逸脱した場合のペナルティが存在すると考えられるため、信用できる指標になる。
大抵の場合、店員は慣れてくると当初の指導やマニュアルをサボり始める。そのサボり具合は、店員のモラルや善意次第である。なかには、よりよいサービスを追求するためにあえてマニュアルを逸脱する場合もあるかもしれないが、これも稀なケースだろう。
そのため、接客時にマニュアル的な対応をされた場合、少なくともその店員は、他の場所でもマニュアル的な対応をする可能性が高い。そういった店員が多い場合、その店全体がマニュアルを遵守している可能性が高いと言えるだろう。
店員がまかないを食べている
これは、店員に動機を与えるパターンである。
これは、今までの監視によるインセンティブとは異なる方法による動機づけである。
店員がその店のまかないを食べる場合、大抵、他の客に提供されるものと同じようなものを食べることになる。同じ食材、同じ調理過程、同じ食器を使うことになる。よって、店員は、「どうせ客が食べるのだから適当でいいや」といった発想ができなくなる。要するに、自分でも食べる以上、全体的な衛生管理に責任をもつようになる。
店員がまかないを食べているかを確認することは難しいだろうが、開店前後や忙しくない時間を覗いたり、その店のSNSやブログを見てみるとわかるかもしれない。
まとめ
現状、完全に人の手を離れた自動化が行われている店はない。そのため、工程のいずれかに人の手が関与しており、リスクも存在する。
したがって、現状では、店員が衛生管理を徹底するような動機づけを行うしかない。その動機づけの方法として、上述したように、管理者の監視か、店員にもリスクを共有させるという方法がある。
ただし、数少ない例外として、店員が自発的に、自身の経済的利益とは無関係に、その店の利益のために働いている。あるいは、非常に高いモラルをもった店員が偶然集まっているという場合もないわけではないだろう。
最後に
以上のような考えは、少し悲観的すぎるかもしれない。現状、まだモラルの高い人間は多いかもしれない。経済的な見返りなく、純粋にこの店を良くしたい、お客様に少しでもいい思いをしてもらいたいと思う人がまだ多く存在するのかもしれない。それは非常にいいことだ。
だが、そういった人間は今後おそらく減っていく。その原因は、人手不足による人材の質の低下、外国人労働者の増加、貧困化、社会の分断による個人主義の加速などである。このような原因により、おそらく、社会はよりシビアになっていく。余裕も無くなっていく。当然、金銭的見返りのない善意は、限られた場面でしかみられなくなっていくだろう。少なくとも、飲食店では見られなくなると思う。
もちろん、このような未来が来ない方が望ましい。ただ、こうした未来が訪れる兆候はあるのだから、それを見据えて、対策を練った方がいいのだろう。