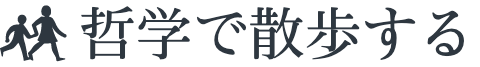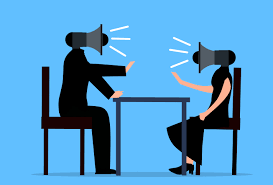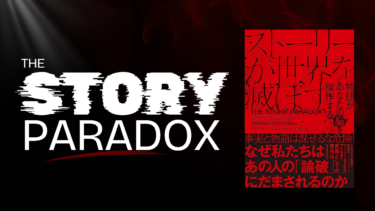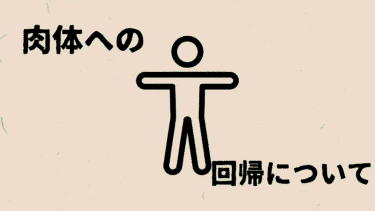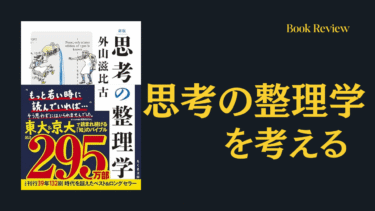この記事では、社会が暴力的になる背景を分析する。
昨今、社会は徐々に暴力的な傾向を帯び始めていると思われる。世界各地で分断が叫ばれ、違う立場の人間が互いを罵り合うというような光景は珍しくない。そういった政治的な領域だけではなく、日常生活においても、従来の調和を重んじる人間関係から、より直接的で対立を厭わない人間関係に移行しつつあるように感じる。
「意見が合わない」や「対立を厭わない」ということそれ自体は、悪いことではない。さまざまな人間がいる以上、それは避けられないことである。しかし、こういった事象が起きる根底に、潜在的な暴力的な衝動の高まりがあるのだとしたら、それは問題だろう。
この記事では、人々の不満を高め、暴力的衝動を駆り立てる社会的要因を分析する。その要因として、この記事で挙げるのは、万人の平等や権利をうたう理念への反発、とくに社会的弱者への支援に対する反発である。この反発とは何なのか、なぜ生じるのか、その結果、なぜ暴力的傾向をもつようになるのか、といったことを論じる。
社会的弱者への支援の前提
第一の前提 万人の幸福の理想
大前提として、万人が、立場やさまざまな力の強弱に関わらず、幸福に生きられた方が良い。そこには、さまざまな事情によって、社会的にハンディキャップをもつ人々も当然含まれる。これを理想とすることに反対する人はいないだろう。
第二の前提 隣人愛や相互補助の存在
なぜ、人々は社会的弱者を支えるのか。
それは、第一に人間には、困っている人を助けようという隣人愛があるからだ。
第二に、働く能力があるか否かは、偶然に左右されるからだ。働けない人々は、それを選んだわけではない。また、いつ自分が社会的弱者になるかわからない。そのため、相互補助が必要である。
ゆえに、社会は弱者を支援するのである。
第三の前提 弱者支援にかかるコスト
こうした弱者支援の理念は、現在の日本社会において不完全さを含みながらも、実現されている。
事実、万人には、生存する権利が憲法上保障されており、それを体現する各種の公的保険やセーフティネットが多く存在する。
こうした理念とその実現が事実であるのと同様に、この理念の実現に、相当のコストがかかっていることもまた、事実である。社会的弱者支援のために、誰かがその理念を支えるための、犠牲を払っている。その誰かとは、一般的な市民である。彼らは、原則として、この理念に賛同しているため、犠牲を払うことにも同意している、とされている。
前提の崩壊
従来、一般市民は、「社会的弱者には権利があり、社会の成員は彼らの権利のために負担をしあう」ということに賛同してきた。現在も多数の人々は、この理念に賛同していると思われる。しかし、従来に比べ、この理念への反発が強まっているとも思われる。その理由は、上記の前提の崩壊にあるだろう。
経済的な貧困化
まず、社会的弱者を支える一般的な人間の経済的な余力が少なくなったことが挙げられる。経済的な余力が減ると、自分の生活で目一杯になる。当然、他の人の生活を負担することへの抵抗が強まる。とくに、社会的弱者は、自身で稼ぐことができない。なぜ、働いていない者のために自分たちが苦しい思いをしなければならないのか、と思うようになるだろう。
権利とその内容の相反
そもそも、権利とその権利による利益は、相反している。
なぜならば、権利が保障する生存権は、誰か別の人間の支えがなければ成立しない。にもかかわらず、この権利は、「生まれながらの自然の権利」として、誰もが無条件にもっている権利であるとされているのである。
では、どちらが優先されるべきなのか。権利の方か、それとも権利の条件か。言い換えれば、理念か現実かである。おそらく、この立場の違いが、いわゆる左派と右派の違いなのだろう。
しかし、いずれにせよ、この権利とは、社会が全体として、社会的弱者に富を分配することができるほど十分に富を生み出しているときに限って、初めて現実となるということは動かし難い現実である。
権利が危機に瀕することによる対立
権利はあるが、その権利を支えることが、社会的な貧困化によって徐々に厳しくなってきている。すると、権利を主張する社会的弱者と、それを支える人々との間の対立が生じるようになる。
その理由は、一般市民と社会的弱者の双方にある。
まず、社会的弱者の権利を支える一般市民は、ほとんどの場合、自分の懐が痛まない程度の他者への支援はするだろうが、自分の生活を犠牲にしてまで、自分が稼いだ富を他人に、それも働いていない他人に分け与えようとはしない。したがって、一般市民が生活に困窮し始めると、徐々に、彼らの間で、社会的弱者に対する風当たりが強まってくる。たとえば、弱者支援のために徴収される金が高すぎるといった不満や、弱者が過度に優遇されているといった声である。
一方の、社会的弱者にとっては、そういった一般市民の声を聞き、自分たちの生存権が脅かされていると思うようになる。すると、自らの権利を守るために、より権利を声高に主張するようになる。彼らを支援する人々も同様である。
過度な自己中心化
一般市民と社会的弱者の対立が激化すると、双方が過度に自己中心化することになる。
一般市民の側は、権利や相互補助といった理念を忘れ、自分の生活・利益のみに集中することになる。
社会的弱者の側は、権利による福祉が、他者によって賄われていることを忘れ、それを当然のものとして主張するようになる。
理念の崩壊と力への回帰
以上で、社会が経済的に困窮することで、ごく自然な流れとして、一般市民と社会的弱者が対立することを示した。
この対立が深まると、どうなるのか。おそらく、一般市民は社会的弱者に対して、敵対心を抱くことになる。なぜならば、社会的弱者は、一般市民による援助に頼っていながら、自分には援助を受ける権利があると声高に主張し、一般市民の援助に感謝するどころか、自らの権利を保護するために、彼らを批判するからである。こうして、社会に敵対心という暴力的な心理が出現し始める。
こうした敵対心は、弱者支援の思想そのものに向けられることになり、一般市民の思想は「社会的弱者の生活よりも自分の生活」という自助の方向へと進むことになる。すると、従来の左派的な権利重視の思想が、理想論であり、綺麗事であると批判をされることになる。
その代わりに生じる価値観は、「自分のことは自分で面倒を見る」という独立志向と、強者に対する礼賛である。
この独立志向と強者礼賛は、連動している。なぜなら、独立志向は、他人に頼らず、自分で自分を支えることを理想としているが、自分を支える力はそのまま他人を従える力に転化しうるからである。そもそも独立しうるためには、他者から自由になることが必要であり、それはそのまま他者より優越することである。
このようにして生じる思想の究極は、「弱肉強食」の思想である。この思想は、力のない者が、権利を主張することを許さない。発言が認められるのは、現実的な力を持つ者だけである。このような「力」が価値基準となる社会では、力を根拠に他人を支配することも正当化されるだろう。つまり、社会は、暴力的になるのである。
現在の社会
現在の日本社会は、どうであるか。社会の困窮は進んでいる。そして、おそらく、一部の社会的弱者に対する敵対心が顕著になっている。その結果として、暴力的な心理が現れてきてもいるだろう。
これが加速していき、弱者全般に対する敵対心となるのか、そして、自己責任と強者礼賛の思想へと変化していくのかは、今後の社会の行方を見守る必要がある。