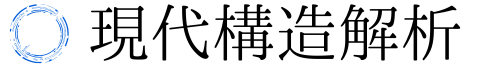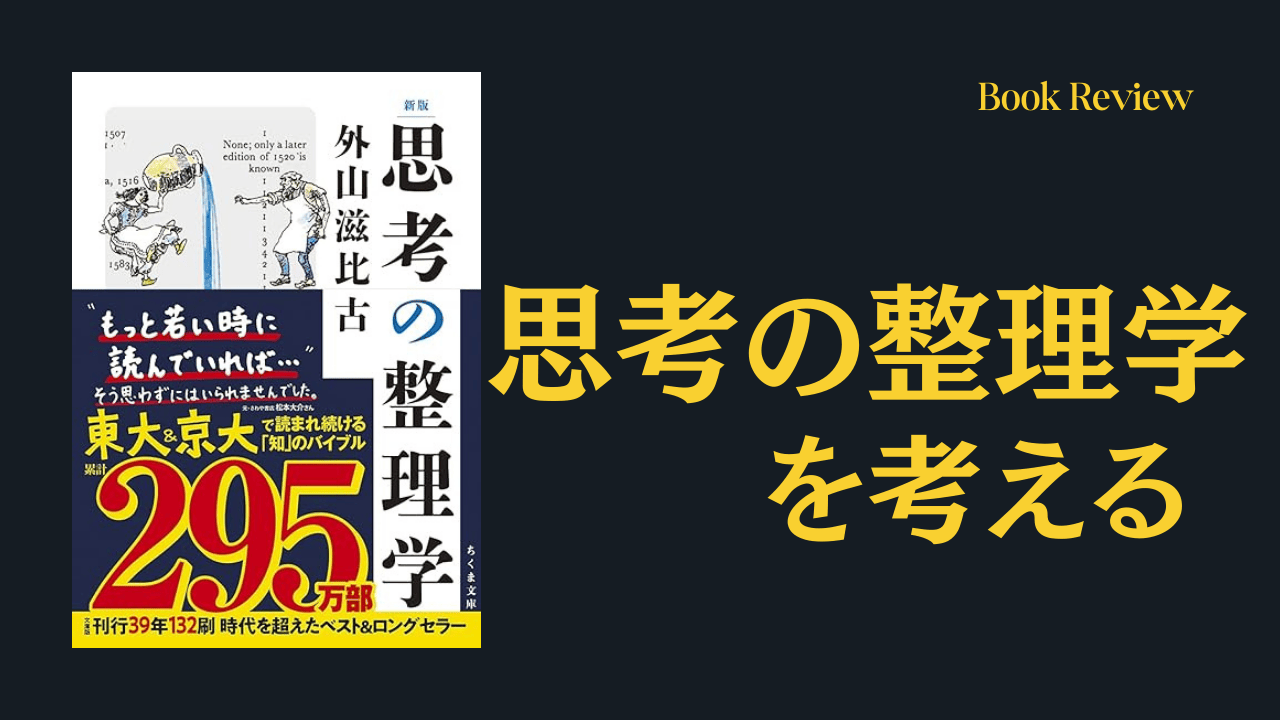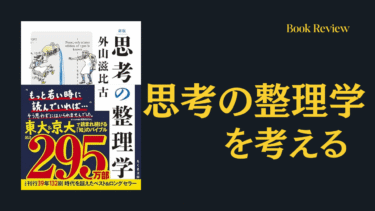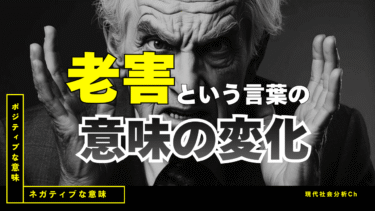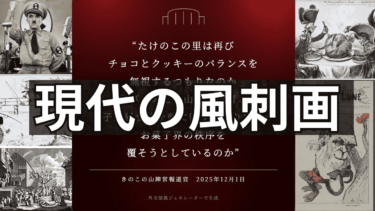『思考の整理学』の第二章について論じていく。この箇所では、アイデアの作りかたが論じられており、興味深い点が多い。
ただ、本書はエッセイのような形式になっているため、まずは内容を構造的に整理してまとめたいと思う。そして、その内容をもとに、発展的に考察をしていこうと思う。
本記事ではまず『思考の整理学』第二章を構造化し、まとめていく。
アイデアの作り方の構造
アイデアの作り方について論じられている第二章は、以下のように分類し、まとめることができるだろう。
| 趣旨 | 該当箇所 |
| (1)独自のアイデアを得る | 「醗酵」「寝かせる」 |
| (2)他のアイデアと調和させる | 「カクテル」 |
| (3)アイデアの混ぜ方=(1)(2)において重要なこと | 「エディターシップ」「触媒」「アナロジー」「セレンディピティ」 |
このように、第二章は、(1)と(2)でアイデアの作り方について概括的に論じ、(3)で後から作り方を詳述しているという構造をとっている。
以下、その中身についてみていく。
アイデアの作り方の概要
(1)独自のアイデアを得る
まず、考えるテーマについて、疑問点や興味のある点を見つける。これを着想を得るための素材とする。本書では着想の作り方をビールの醸造にたとえおり、この素材は、ビールでいうところの麦にあたる。
次に、テーマとは関係のないところから着想のヒントを得る。このヒントはどこにあるかわからない。とにかくテーマとは異なるところからこのヒントを得て、それと素材を混ぜ合わせる。このヒントは、ビール醸造でいうところの酵母にあたる。
最後に、素材と酵母を寝かせておく。どれほど寝かすかはそのテーマや着想の規模によるが、大きなテーマはそれだけ長い時間寝かす必要がある。
(2)他のアイデアと調和させる
(1)で作られたアイデアは、独自の発想である。この独自の発想は、ともすれば独善的になりやすい。そこで、すでに存在する自分と似たテーマを扱っている他のアイデアを参照し、それらと自分のアイデアを調和させる必要がある。
このときに、自分のアイデアを贔屓にして、それを補強することだけを目的として、他のアイデアを参照してはならない。なぜなら、それは結局は独善的であることに変わりないからだ。
そうではなく、自分と似たテーマについて、自分とは異なる複数のアイデアも取り合わせながら、自分のアイデアと調和させる。そうして、自説を作り上げる。
本書では、この調和をカクテルに例えており、カクテル法と呼んでいる。
(3)アイデアの混ぜ方
上の概要の(1)と(2)の両方において、「混ぜる」ことがポイントとなっている。
(1)においては素材とヒントを混ぜること、(2)においては自分のアイデアと他のアイデアを混ぜることが論じられている。
この混ぜることについて、本書は以下のいくつかの観点から論じている。
混ぜる順番
混ぜる順番は、エディターシップにおいて重要である。
エディターシップとは、小説や詩を集めて並べる編集のことを指している。短編集や雑誌などの個々の作品をまとめた作品集において、個々の作品が第一次的創造であり、エディターシップは第二次的創造といえるほど重要である。
その理由は、個々の作品をまとめる際に、その並べる順番を誤ると、その全体が凡庸なものになっていしまうからである。逆に、収録されている個別の作品は今ひとつでも、その並べ方によって、全体として優れたものになりうるのである。
これは、アイデアについても言えることである。一つ一つのアイデアが凡庸でも、その組み合わせ、すなわち混ぜ方によって、最終的な自説が優れたものになりうるのである。著者はこれを「知のエディターシップ」と呼んでいる。(p.52)
混ぜるときの主体の姿勢
どのような姿勢でアイデアを混ぜるのかも重要である。
素材と酵母を混ぜたり、自分のアイデアと他のアイデアを混ぜるのは、アイデアを作ろうとする自分自身である。このアイデアを作る主体のあるべき姿勢を、著者は「触媒」のアナロジーで論じる。
触媒とは、何らかの物質同士の化学反応を促進させる物質であり、触媒自体はその反応前後で変化しない性質をもつ。
これと同じように、アイデアを混ぜる主体は、そのアイデアに自分自身の主観を混ぜ込んではならない。あくまでも、アイデア同士が混ざり、結合し、新たなアイデアが生まれる場所を提供するという中立的な役割に徹するべきである。
なぜなら、主体がアイデアの生まれる現場に関与し、そこに主観を混ぜ込むと、独善的になり素材やアイデアのもつ可能性が狭められてしまう。主体が中立的に没個性として振る舞うことで、アイデア同士がいわば自由に、独創的な結合をすることができるのである。
何と何を混ぜるか
アイデアを作るときに、どのようなアイデアを混ぜ合わせればよいか。特に、最初に自分のアイデアを作るとき、素材とヒントはどのようなものを組み合わせるべきか。その組み合わせの手法としてアナロジーが有効である。
アナロジーとは、類比や類推と訳され、ある事柄に存在する法則や構造を他の事柄に当てはめて考えることである。
たとえば、カレーは寝かせると美味しくなる。これは、寝かせることで食材の味が溶け出し、全体の調和が増すからであると考えられる。このことと、習得した知識をアナロジーとして考えることができるだろう。知識は脳内に取り込まれ、時間が経つと、それぞれが収まるところに落ち着き、全体としてネットワークが機能し始める。
このように、全く別の事柄にある法則や構造をヒントとして、それを自分の考えているテーマに当てはめることで、自分独自のアイデアが生まれることになる。これが、素材と酵母の関係である。
そして、このような別の事柄・領域が自分のテーマの役に立つということは、偶然であることが多い。たまたま関心を持った分野が、予期せぬ形でヒントを与えてくれるのである。この偶然の出会いをセレンディピティという。
自分のアイデアを作るために、時間が必要で、またそのテーマに限らない関心が必要とされるのは、このセレンディピティを生じさせ、それが頭の中で自分のテーマと結びつくために、整理する時間が必要だからであろう。
まとめ
以上で、『思考の整理学』第二章を構造的にまとめた。構造としては、自分のアイデアを作る方法、それを他のアイデアと混ぜてより客観的なアイデアにする方法、そしてそれらを行う際の心得に分けられるだろう。
そして、この章を通して著者が強調していることは、「アイデアを寝かせること」と、「主観による独善を避けること」だろう。
アイデアを作ろうと力むとむしろアイデアが出なくなる。自分の興味関心を自由に伸ばし、自分にもアイデアにも自由と時間を与えることが、アイデアを生む最大のポイントである。これが著者のアイデアに対する基本的な考え方を表しているといえると思う。