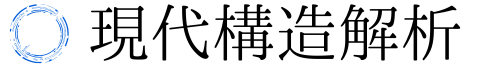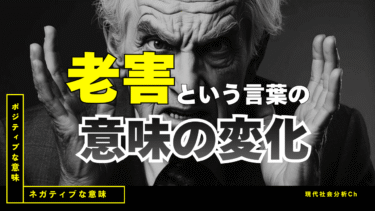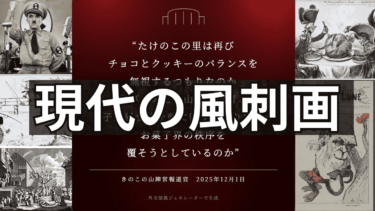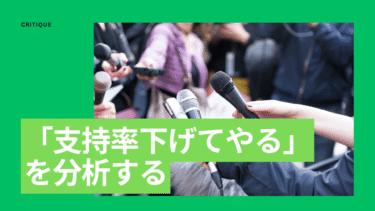サッカー、野球、バスケ、テニスなど、多くのスポーツにおいて、チャンピオンを決める時には、同じ対戦相手の試合を複数回行う。その理由は、複数回試合を行うことで、本来の実力で決着をつけやすくするためだろう。
一回きりの試合では、純粋な実力以外の様々な変数の影響を受けやすい。うまくいけば実力以上のパフォーマンスができるだろうし、逆に下手をすれば実力を下回るパフォーマンスになることもあるだろう。
これは、スポーツに限らず、日常生活でもいえることだろう。何かしらの発表の場や、テスト、あるいは日々の集中力についてもこういった波がある。
こういった調子の波について、俗に、うまくいった場合を「上振れ」、逆にうまくいかなかった場合は「下振れ」という。
今回は、この調子の波である上振れや下振れについて考え、どうすれば調子の波を減らし、成長できるかを考える。
調子の波
調子には波がある。上振れるときもあれば、下振れるときもある。それはおそらく、トップレベルのアスリートなどの、自らの限界に近いパフォーマンスを出す必要がある人ほど、避けることができないことであると思われる。
普段、8割程度の力で作業をしている人は、自分のリソースの残り2割に余裕がある。ということは、どこかに不具合があっても、それを迂回したり、それほど高出力で動かす必要がない。それゆえに、不具合・不調の影響が表面化しにくく、パフォーマンスに差が出にくい。すなわち、調子に波がでにくい。
しかし、自分の限界に近いパフォーマンスを出すということは、自分の肉体的・精神的なリソースを最大限使う必要がある。となると、細かな不具合や不調が、全体のパフォーマンスに影響を与えやすくなる。それは、高速道路を利用するときに、自動車にいつもよりも細かな点検が推奨されていることと似ている。高い出力を出す時には、より細部の状態がものを言うのである。
また、常に高い出力を出し続けていると、身体や精神に高い負荷がかかる。その負荷の影響で、ダメージが蓄積し、パフォーマンスの調子に波を作ることもあるだろう。
調子の波を小さくするには
トップアスリートでない多くの人々にとって、常に限界ギリギリの高いパフォーマンスをする必要はない。そして、一時的に高いパフォーマンスを発揮するよりも、継続的に安定したパフォーマンスを発揮できた方が望ましいだろう。
であるならば、上記したように、ある程度自分にとって余裕のある出力にしておいたほうが良いだろう。そうすれば、調子の良し悪しの影響を受けにくく、一定のパフォーマンスをすることができる。
たとえば、何か勉強を行うとして、1日〇〇ページとか〇〇時間といった目標を立てる時に、その目標が常にある程度余裕のある目標であることが望ましい。そうすることで、コンスタントにこの目標を達成していくことができる。
調子の良い日にはたくさんやり、調子の悪い日にはやらないといったことをすると、調子の波を作ってしまう。
たとえば、作家の村上春樹は、コンスタントに執筆を続けるために、どんなに筆が進んでも、あるいは進まなくても1日に書く文字数を決めており、それを毎日欠かさず続けるという。こういった日々のルーティンをもつスポーツ選手は数多くいるが、ルーティンを作ることは、スポーツ選手以外にも、調子の波を作らないという点で有効なのだろう。
波を作らず、実力を高める
このように、自分にとって余裕のあるルーティンをもつことが、調子の波を小さくすることにつながるのは確かだろう。だが、それを継続することは、実力の向上につながらないような気もする。自分にとって余力のあることをやり続けても、自分の成長を実感しづらいからだ。
ではどうするか。
ここで重要なのは、多くの人にとって、成長の結果として得たいものが、不安定なパフォーマンスの上振れであるよりも、安定したパフォーマンスであることだ。たとえば、10回に1回100点のパフォーマンスが出せるよりも、80点のパフォーマンスを毎回出せたほうがいいだろう。
このように考えるならば、まず必要なのは安定性であり、「波がない」ということになる。よって、まずはパフォーマンスを安定させるために、余裕のあるルーティンを作ることを優先する必要がある。そして、そのようなルーティンが体に染み付いたあとで、徐々にルーティンの内容をハードなものにしていけばいい。
余裕があるとはいえ、ルーティンを毎日こなせば、確実に自分の実力は向上し、余力の幅が広がる。あとは、その広がった余力の分だけルーティンの内容をハードにしていけば、自分にとっての体感の余裕は変わらないことになる。
こうして、波を作らず安定したパフォーマンスを発揮するように、ゆっくりだが、着実に成長していくことができるだろう。
一夜漬け
以上の方法の真逆のものが一夜漬けである。これは、パフォーマンスに波を作る最も顕著な例だろう。
一夜漬けでは、締切間際に急激に高いパフォーマンスを発揮させ、それがなんとか終われば、疲れや解放感のせいで一気に何もしなくなる。これは、調子に波を作らない習慣にとっての反面教師といえるだろう。
まとめ
上記した方法は、安定した調子を維持し、徐々に実力を高めていくものである。そのため、時間がかかる。近道とはいえないやり方である。そして、必ずしも正しいとは限らない。一夜漬けのように短期間で高出力を出した方がいい場合もあるだろう。
だが、おそらく人生単位で見たときに、安定して結果を残せるのは、波の少ない方だろうと思う。それは、先人がいくつものことわざや寓話などで、継続の大事さを説いていることからわかるだろう。