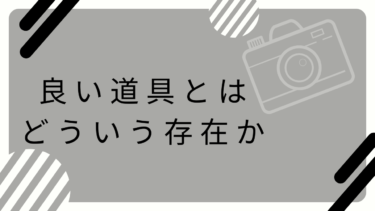哲学チャンネルはこちら↓
初めに
さて、前回の続きです。前回はものの見方を二つに分けました。一つは、科学的で客観的なものの見方で、もう一つはそれではとらえきれない人間に対する見方でした。
科学的なものの見方は、中立的に観察された対象として存在を見出すというもので、そうした存在は、観察者に対して独立、自立した存在として存在するとされたのでした。それに対して、人間は、自分が自分であるということを、生きることによって実現しています。人間は鏡に映った対象として自分を見出すよりも前に、さまざまな欲求を抱え、そのためにさまざまな行動を行い、さまざまな日々の糧に支えられて生きています。対象として「自分は存在する」と意識するよりも前に、私はすでに何かをしているのであり、直接的に生の中にあるのでした。
この生の次元において、人間は主観的に生きています。主観的であるとは、何かと特別な、自分にとっての関係を結んでいるということです。長年着続けた服は、もはや自分の体の一部のように思えるかもしれません。このように、主観的な、直接的な生の次元においては、「自分にとって」の世界が広がっており、その世界がどのようであるのかが、日常の生活を決定づけます。
今回の話では、その日常世界を見つめ直すために、その外側と関係するということ考えました。
日常性とその外側
日常性とは、私がその中で生きている環境です。この環境は、主観的な世界として、馴染みのあるものとして見出されます。それは予測可能な世界です。人間は、その世界の中で生きています。生きるとは、相互依存的に、世界と交渉することです。その交渉によって、人間は環境に馴染み、適応します。つまり、その環境に適したあり方に形作られていきます。これが、環境によって人間が規定されるということです。
このことは、慣れや熟練、習慣化などさまざまな言葉で言い表されます。これらの言葉は、身体的な動作に用いられることのほうが多いかもしれませんが、このことは精神にも当てはまります。たとえば、馴染みのある場所に安心するのは、精神的にその場所に慣れているからであるといえるでしょう。
このような、精神的な慣れが集合して全体としての日常を作っているといえます。日常は環境に適応した自分の枠組みのことで、それは人間に安定を与えます。その安定した日常に亀裂を入れるのは、未知のことがらです。そして、この未知に対して人は不安を感じます。不安とは未知という日常の安定性を脅かすものに対する感情的な反応であるといえるでしょう。
一般的に不安は、何か良くないことが起きそうなときに、感じるとされているかもしれません。たとえば、テストの結果や、健康診断の結果が悪そうだと予測可能なときに、不安を感じるかもしれません。しかし、この不安とはおそらく、テストや検診の結果がもたらす予測不能なこと、つまり、予測可能な結果の先にある予測不可能なことに対して、感じているのではないでしょうか。もっとも極端な例は、死の不安です。人は死について予測することはできないため、死とは予測不能性の最たるものであるといえるでしょう。予期される苦痛と予期し得ないものに対する不安は別のものであると考えるべきだと思います。
つまり、不安とは、被害の予期であるというよりも、より漠然とした感情で、それは日常の堅固さ、自明さを崩しうるものに対する恐怖といえるでしょう。あらかじめその未知のものに対して期待したり、憂鬱を感じるのは、それが実は新しいものではなく、何か良いことや悪いことが起こりうるという予測が立てられるもの、すなわちある程度馴染みのあるものであるということです。この先にの見通しが全く立たない未知の物事に対して、不安は感じられるのです。
このような不安は日常を反省させます。なぜならば、不安は日常が脅かし、その自明性が崩されることで初めてそれが日常性として、生の条件として機能していたことがわかるからです。経験的に言えば、ものごとが軌道に乗っているときには、その予測可能性のなかで安心できますが、先行きに不安を感じるから、今までの人生を振り返るのではないでしょうか。失って初めて気づくというのもこのことでしょう。
未知のものが日常性に対立することで、不安を覚え、無自覚的だった日常性を浮かび上がらせることを述べてきました。これに対して、対立的ではない仕方で日常を審問する可能性があります。それが、この回でも扱った朝日や富士山などの美しいものです。美しいものは、人間に対してその日常性を超えた領域をもたらします。これは不安が日常性に対立するのとは異なる方法で、日常性の外を示します。
美しいものに出会うとき、人は我を忘れ、その存在に圧倒されます。美しいものは、日常的なものの見方を停止させ、日常性を超えた高みから、別の意味を示します。この出会いにおいて、時間的なもの、連続したもの、すなわち日常の中で繰り返される予測可能な時間の流れが停止し、美しいものの前に全ての歴史性が消失します。この点で、美との関係とは、非時間的であり、そのほかの事物との関係を締め出します。よく美に対して用いられる表現として、「時間が止まったよう」とは、「息を呑む」などといったものがあるのは、美が人間に対して、日々の日常的な関心を停止させ、全ての注意を向けさせることを示しているように思えます。
この関係は、排他性といってよいでしょう。美は私を取り囲むものとの関係を中断し、日常の関心の連続性を中断します。つまり、美はすべての日常性を一時中断し、私の全てを賭けて関係を結びます。そのような関係にあるとき、美を規定したり、その価値の根拠をその他のものに見出すことはできません。なぜなら、美との関係は、閉じた排他的な関係であり、他の存在の登場する日常性の一時中断であり、他の存在はそこには介入しないからです。
美との関係が、私と美しいもの以外を拒み、排他的であるのならば、それは日常の外にある完結した関係といえます。つまり、それは日常性から独立した世界と私の関係となります。そして、美が、日常の連続性を解体し、その瞬間とその美しいものという極限に全ての意味を凝縮するため、日常性の外側にあり、日常性の上に位置するといえるでしょう。つまり、美は一方的に日常を審問し、その意味の体系を、くだらないものとして解体してしまう力を持っています。
しかし、美のこのような機能によって、日常が無意味なものとなってしまうわけではありません。美の本質は、その排他性であり、時間や関係をもたないことで、その一点に全てを集約しているというところにあります。そのため、美は歴史を持たず、つねに、そのつどの究極的な根拠として君臨します。つまり、美とは関係の切断として、日常に対する否定性として機能するといえます。そのため、日常という冗長さ、連続性、幅をもった時間といくつもの関係の拡散という地盤がなければ、美は作用しないということです。
日常の外で、その多元的な意味性を脱出して、人生を究極的意味の上に据えようとする試みは、おそらく正しいものとはいえないでしょう。「ホンモノ」や「青い鳥」を探すことに人生の意味を集約させることは、おそらく無責任とさえ言えるのではないかと思います。なぜならば、集約された意味とは、美との関係であり、それはその関係以外の否定であり、排他的であるからです。つまり、何かに対して集中するということは、必然的に他のものを切り捨て、無関心にとどまり、それを瑣末なこととして自分の世界から追放するということです。究極的なものに集中し、他のものを切り捨てるという姿勢は、自己実現という美辞麗句に隠された暴力を暴くものなのかもしれません。ただ、今回はこのことについては深く踏み込めません。
今回の問題は、美しいものが日常性の外からやってきて、その日常性を一時停止させる役割を持っているということです。そして、その一時停止が、日常から人間を一旦遠ざけ、新鮮な目で日常を見直させるということです。美との関係が日常性を超えてしまうことを避け、美をあくまでも日常との関係で捉えるということが大事だと思われます。このことは、フィクションの世界が人を現実に返さねばならないことと同じです。
まとめ
美について論じるつもりが、美の危険性について長々と論じることになりましたが、最後にもう一度、美の肯定的な機能についてまとめます。
日常性は、前述したように、暗黙の前提として、無意識的に受け入れられています。そのため、この日常性にあらためて注目することは難しいのです。この日常の当たり前に注目するには、その当たり前が脅かされるか、その当たり前とは全く異なる関係を結ぶかのいずれかが必要でしょう。そして、美との関係とは、日常の外を見せてくれる関係であるということです。
最後により限定的な人生の局面について。日常の世界は複雑で面倒なものです。時に、複雑性の絡まった糸が、人を無意識のうちに行動不能に縛り上げるときがあります。そんな時に、その糸を断ち切って、また新たに繋げ直す役目を担うのが、美なのだと私は思います。あくまでも、私の意見であるということを最後にこの回の振り返りを終えたいと思います。