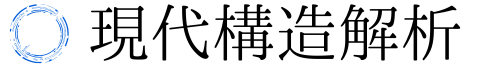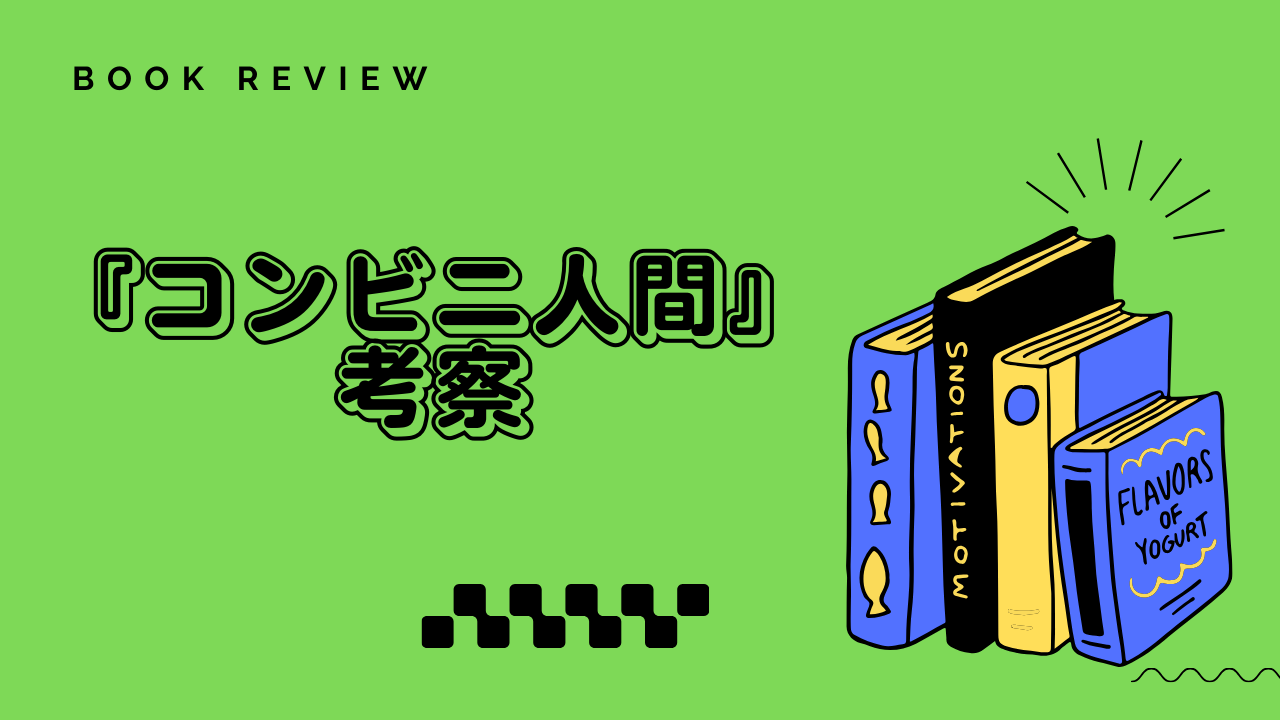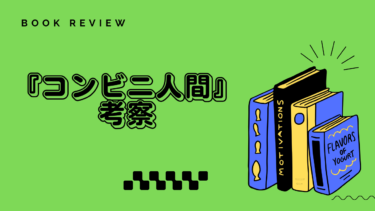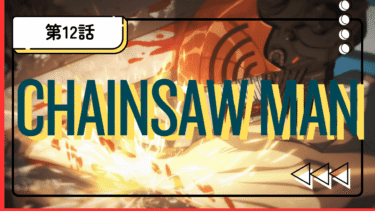今回は、村田沙耶香著『コンビニ人間』の中心的なテーマである「正常」と「異常」の違いについて考察したいと思う。
本書を通して、「普通の人」というときの「普通さ」とはいったい何なのか。そして、主人公の小倉は「異常」であるのか。その「普通」と「異常」とは何であり、誰が決めたのか。「普通」であることは正しく、「異常」であることは間違っているのか、といった疑問について、少し哲学的に考えてみたいと思う。
作品のあらすじ
本書のあらすじをごく簡単にまとめる。(以下ネタバレ注意)
幼少期から人の感情がわからず、人と同じものに関心をもつことができない主人公の小倉が、唯一関心をもつことができた職業がコンビニのアルバイトである。しかし、周囲の人々は彼女のコンビニバイトへの関心を、「まとも」とは扱わない。そして、周囲は、彼女に「まとも」になってほしいと願ったり、「まとも」でない彼女に対して侮蔑的な態度を取る。彼女はなるべくその「まとも」であれという期待に応えようとし、白羽との同棲により、それを一時的に実現するも、それに馴染むことができず、やはりコンビニバイトという彼女の世界へと戻っていく。
小倉と白羽たちとの違い
本書の登場人物は、「まとも=普通=正常」な人と、「まともじゃない=普通でない=異常」に分けることができる。「まとも」なのは、白羽たち他の登場人物であり、「まともじゃない」のは主人公の小倉である。
作品を通して、この「まとも」な人たちと、「まともじゃない」主人公は、お互いに関わり合うものの、両者には埋まらない溝がある。
では、本書における「まとも」や「まともじゃない」とは何なのか?
白羽たち:「まとも」側
本書に登場する人物たちは、小倉を除いて、皆同じ「まとも」・「正常」に分類できる。
確かに、白羽や小倉の家族、同級生、コンビニの店長らには違いがある。特に白羽を「まとも」と扱うことには抵抗があるかもしれない。実際、彼は小倉に暴言を吐くし、コンビニバイトは底辺である(p.71)とか、女性は結婚しなければまともじゃない(p.93)とかといった趣旨の発言をする。
しかし、作中では、小倉以外の大抵が、皆同じような価値観をもっている。コンビニ店長や他のバイトも、コンビニバイトを見下すような発言をするし、一見理解のあるように見える同級生らも、ある同級生の夫が小倉の生活に否定的な発言をしたとき、「場をとりなす」(p.83)ことこそすれど、擁護はしなかった。
つまり、彼らは皆、程度の差はあれど、共通の価値観をもっており、「同じ」であり「まとも」に分類できる。
小倉:「まとも」じゃない側
小倉は小さい頃から「まとも」ではなかった。具体的なエピソードはいくつかあるが、動物の死を悲しまなかったり、人の気持ちがわからなかったりした(p.12-15)。
そして、その「まとも」でなさゆえに、周りを困らせた。特に彼女の母親を困らせた。小倉は以降、母親や周囲の人間を困らせないように、自ら何かをすることはなくなった。クラスでも誰とも話さず、息を潜めるようにしていた。なぜなら、自ら発言したり行動したりすると、再び相手を困らせることになると考えていたからである。
小倉のこうした行動をする原因は、彼女が他人に「共感できない」ということにあるだろう。彼女には、人の悲しみがわからないし、人がなぜ自分を非難するのかもわからない。
通常、人間は傷ついた人間に「かわいそう」とか「痛そう」といった共感をすることで、「人を傷つけてはいけないのだ」という規範を内面化する。しかし、彼女は他者に共感することができない。
そのため、小倉には他の人の価値観を理解できないし、他の人と同じ価値観をもてない。
ゆえに、小倉は「同じじゃない」し、「まともじゃない」のだ。
両者の本質的な違い
このように、皆と同じ価値観をもっているのが「まとも」な白羽たちであり、皆と違い、共通の価値観をもてないのが「まともじゃない」小倉なのである。
だが、白羽たちのもっている価値観は、上記のように、いまや古いもので、そんな価値観をもっている彼らの方が「まともじゃない」と思うかもしれない。
しかし、本質的な「正常」と「異常」の差は、彼らがもっている具体的な価値観の内容ではない。
たとえば、「結婚するべきだ」といった考えは、今日では非常識なものとされる。人はそれぞれ自ら自由に生きる権利があるとされているからだ。しかし、昔はこの考えが常識だったし、この考えをもっている人が「まとも」であった。であるならば、当時「まとも」とされていた人は、実は「まともじゃない」人だったのか。
そんなことはない。当時「まとも」とされていた人たちは、それが「まとも」とされている価値観だったからそういう考えをもっていたのであり、それが「まともじゃない」とされるようになったら、その価値観は改めるのである。
「正常」の本質
このように、具体的な価値観の中身は、時代や社会によって「まとも=正常」か「まともじゃない=異常」かは異なる。つまり、具体的にどういった価値観をもっているから、「正常」でないと言うことには意味がない。それは、ある社会では「正常」な証だし、別の社会では「異常」である証になるからである。
「正常」さの本質とは、そういった具体的な価値観の内容なのではなく、他者と同じ価値観を共有しようとするかどうかである。
それを表しているのは、白羽たちの言動である。白羽たちは、小倉を「異常」であるとみなすが、彼らはただ単に彼女のことを自身の胸の内でそう捉えるだけではない。彼女が異常であると、周囲に示すように振る舞うのだ。具体的には、彼女に対して直接そのように言ったり、まわりの人間とそのように話したりすることである。
彼らは、なぜ単に自分の中で彼女を「異常」であると思っておくのではなく、そのように振る舞うのか。それは、自分がもっている価値観が正当であると他人に肯定してもらいたいからである。
そのように、彼らは、自らの価値観を他者に表明しながら、その価値観を他者と擦り合わせていく。そして、他者と同じ価値観をもつようになる。この同じ価値観をもつことが、「正常」であることの条件であるからだ。白羽たちが奇妙なほど同じ価値観をもっているのは、彼らが「正常」である証であるともいえるのである。
「正常」と「異常」の原因としての共感
では、なぜ人は、他者と同じ価値観をもとうとするのか。そして、なぜ、同じ価値観をもとうとすることが「正常」であるのか。そもそも、なぜ「正常」と「異常」という区別があるのか。
これらの問いに対しては、さまざまな側面から答えられそうだが、本書に則ると、「人間は共感をする存在であるからだ」、といえる。共感をするということが、「正常」と「異常」という区別を生み出す根源的な要因である、といってもいいだろう。
共感が価値観を共有させるメカニズム
なぜ、「共感」が他者と同じ価値観をもたせ、人を正常と異常に区別するのか。
共感とは、たとえば、「動物が死んで悲しい」、「人が痛がっているとこちらも痛々しく思える」というように、相手の状態や感情を、自分のことのように感じることである。これはつまり、自分が相手に感情移入し、仮想的にではあるが、自分が相手と同一になるということである。
したがって、共感とは、自分と相手を繋げ、自他の区別を乗り越え、自分と相手を同じにするという機能をもっている。そして、これは、理性的なことではなく、感覚的であり、本能的なことなのである。
このような、いわば自他同一化装置としての共感は、本能的に無意識的に自他を同一化させようとする。その結果、共感という装置をもった人間は、他者と同じような価値観をもとうとするのである。
共感の有無=「正常」・「異常」
こう考えると、「他者と同じ価値観を共有しようとする」=「共感する・できる」ということでもある。つまり、「正常」であるとは、「共感する・できる」ということなのだ。裏を返せば、「共感できない」=「異常」ということなのである。
では、その区別をしているのは誰か。それは、共感できる「正常」な人間である。
「正常」な人間たちは、互いに共感しあう。そして、それによって、感情や価値観を共有し合う。そうして、自分たちが同じ感情を共有することを通して、自分たちが同じ人間、仲間であると考える。つまり、共感とは、人間を同じものとして認識させるための識別子であるともいえる。
そして、同じものであろうとする「正常」な人間にとって、互いに感情や価値観を共有できず、互いの同一性、共通性を阻害する存在が、共感できない存在である。共感できない存在は、こうして、共感できる存在、すなわち「正常」な人間たちにとっての異物となり、「異常」であるとみなされるようになる。
「正常」な人々は、さらに、その異物の存在を、共感によって共有しようとするのである。
本書においては、小倉は、白羽たちによって、「異常」だとみなされ、侮蔑される。それは、共感できず、自分たちと同一になることのない小倉に対する彼らの感情的なリアクションなのである。そして、白羽たち=「正常」な人間は、小倉が「異常」であるということを周囲に伝播する。そうして、「まとも」側の人々は、小倉を「異常」として扱うようになるのである。
このように、一般に美徳とされる「共感」とは、共感しない者を「異常」な者として区別・差別する原因にもなりうるのである。そして「異常」な者に対する嫌悪感もまた、共感によって「正常」な者たちに広まっていくということである。
読者への無言の問いかけ
私も含めて、多くの読者は、自分たちが「まとも」であるという面をしている白羽たちの方こそ、「まともじゃない」と感じたのではないだろうか。彼らは確かに、あまり時代とはそぐわない価値観をもって、それによって小倉に干渉している点で、良い印象は抱きにくい。
しかし、そこで、「彼らの方こそ『まともじゃない』」という感想をもったのならば、以上の理論によって、読者自身もまた、小倉を差別する白羽たち同様に、全く同じ構造で白羽たちを差別しているといえることになる。この点においてあなたは白羽たちと全く変わらないということになってしまうのだ。
では、他人を侮蔑し、干渉する人々に対して、それを黙認するべきなのかというと、それも違うだろう。問題は、批判するアプローチである。「正常」と「異常」を分け、感情的に「異常」な存在を貶す、というやり方では、彼らと同じことをやっていることになる、ということである。
大事なのは、表面に出てきている行為の内容なのではなく、それがなぜ行われているのかといった背景も含めた原因の追求である。これをやらずに、単に表面的なことだけを非難していると、今回のように、非難している側が実は非難されている側と全く同じことをしており、自分で自分を非難しているような、いわゆるブーメラン的なことになってしまう。
解決の手掛かり
今回のこの「正常」と「異常」の区別・差別から生じる問題を解決する手掛かりは、おそらく他者の捉え方、他者との関係の方法にあるだろう。
共感の完全な否定ではなく、共感によって他者を自分の延長のように考えてしまうのでもない、他者を他者として自分とは異なる存在で異なる世界に生きているということを前提としつつも、お互いがお互いに正しくあり、かつ幸福であることを願うという関係が望ましいだろう。
そのような他者との微妙な関係、距離をうまく計れるのがおそらく成熟した人間の条件なのだろう。こうしたことをどのように考えるのかということは、『コンビニ人間』という作品が突きつけた課題のひとつであろう。
参考文献